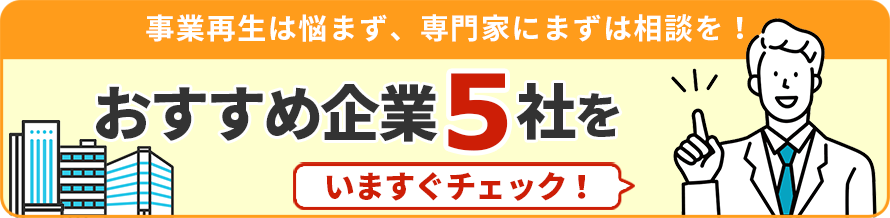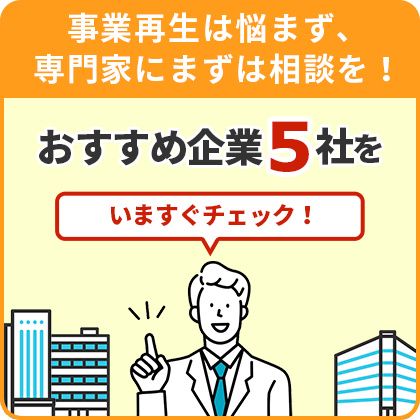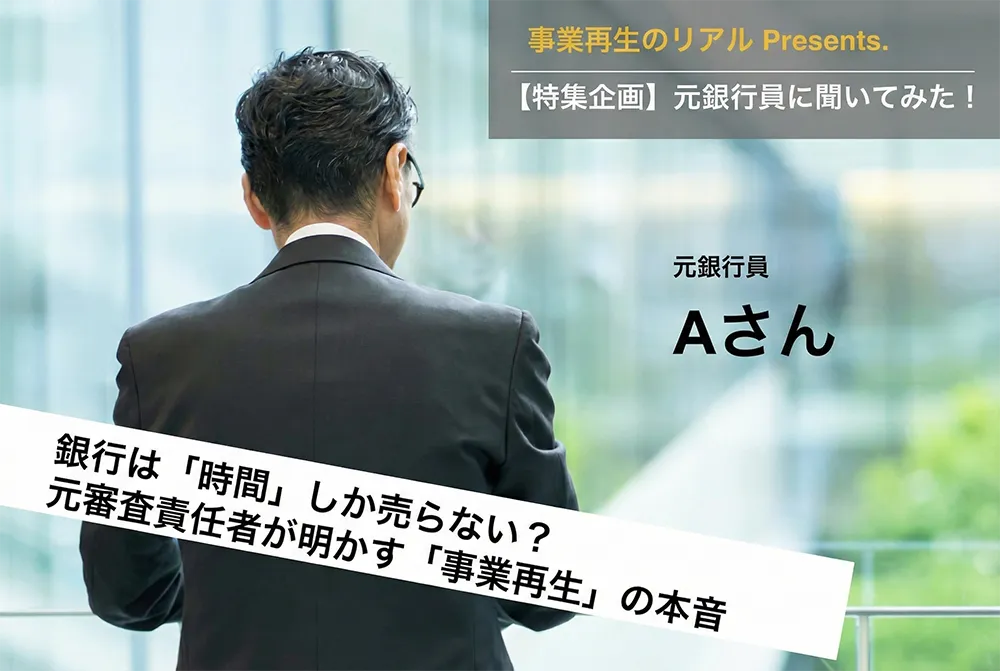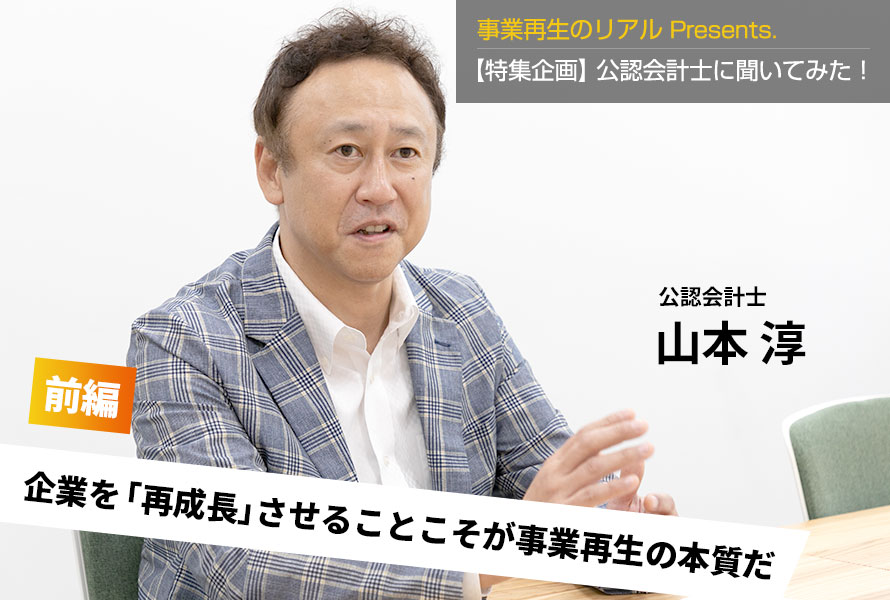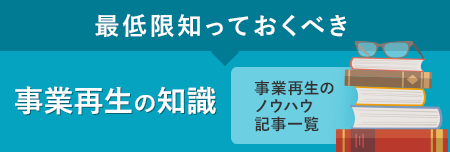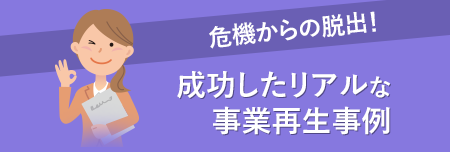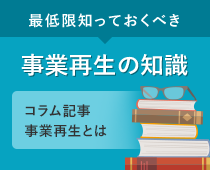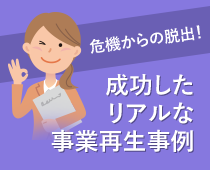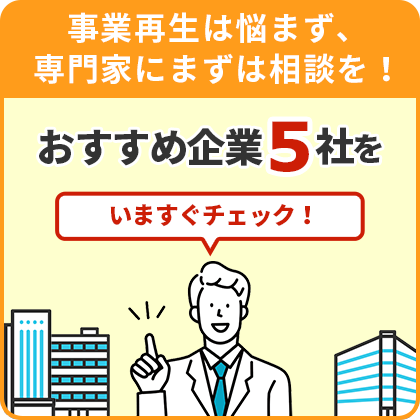2023年06月29日
弁護士の山崎良太先生へのインタビューの後編です。
今回も前編に引き続き、事業再生の領域で経験豊富な弁護士の山崎先生にお話を伺いました。
実際の事例のお話なども絡めて、前編より深い内容についても伺っているので、是非ご覧ください。
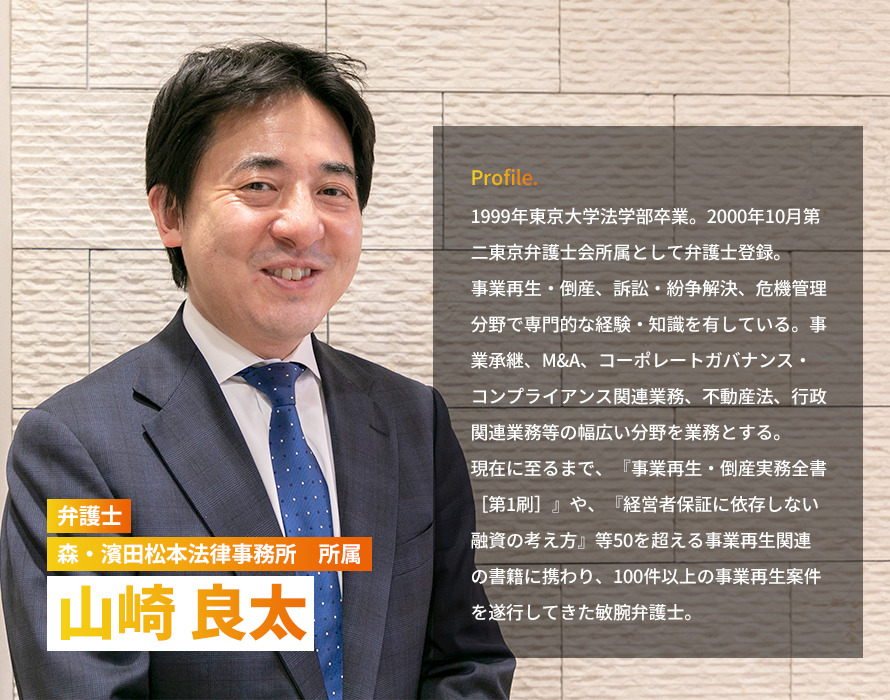
【弁護士が語る事業再生】粉飾決算に手を染めた会社の事業再生
目次 [非表示]
事業再生における信頼関係の大切さ
-依頼者と専門家がワンチームになることが重要-
事業再生では、株主・取引先・金融機関などの利害関係者が多く、各々との調整が必要かと思いますが、お仕事をするうえで大切にしていることはなんでしょうか?
信用してもらってそこから信頼に繋げていく、ということを大切にしています。
依頼者に債権放棄してもらったり、経営者でいるのを辞めてもらったりするので、やはり信用だとか信頼関係を築くという部分が非常に重要です。
それはステークホルダー対応みたいなことが結局は信用補完にもなるし、そこから信頼関係が生まれることで、利害関係者とも信頼ベースで物事を進めていくということができます。
難しいお願いであっても、そこにはルールがあって、相手は人間ですからいろいろな考え方があって、そこを理解をしながら信頼関係を築いて交渉していくのが私の仕事なのかなと思います。
依頼者と信頼関係を築くために実践していることはありますか?
結局、信頼というのは、お互いに歩み寄ろうという気持ちがないと生まれません。
ですから私はまず、会社から依頼を受けたら職場を見学させてくださいということをお願いして、どういうことをやっているのかを実際に見させてもらいます。
そこで社長自身から直接話を聞いていくなかで、昔はこういったことが上手くいっていたとか、会社の強みはどこか、悪くなっていったのはどうしてか、といった様々なことが見えてきます。
そうすると私の中にも、なんとかしてこの会社を守ろうという気持ちが生まれます。
依頼者からしても、そうやって関心を持ってくれたということで話が広がりますし、信頼関係が生まれやすくなるのかなと思います。
だから、まずは実際に会社を見に行くということを心がけています。
会社や工場を見学させて下さいというと、弁護士さんからそんなことを言われたのは初めてだ、と驚かれることがよくあります。
でもコンサルタントの方なら、まず現場を見ますよね。
弁護士も会社を建て直すためのチームの一員として関与する以上、現場をできるだけ早く見せてもらうことが重要です。
寄り添うとか信頼関係を築くためには、まず会社に来てくれるかとか、本当に自分たちのことを理解しようとしているのかといった部分が、会社にとっても大きいのではと思います。
弁護士は本質的な部分で経営のことが分かるわけではありませんが、極限状態の中で、経営の根幹に関わる判断を一緒にするとか、あるいはもう弁護士が決めてしまう場合もあります。
そうなるとやはりお互いに信頼関係が築けていないと難しい部分は多いと思います。
山崎流事業再生の進め方
-複数プランを用意して臨機応変に対処する-
ご自身が思い描いたような計画通りにいかなかったときにはどのように対応されますか?
バックアップとして予めBプラン・Cプラン的なものを準備しないといけません。
考えなければいけないことを並行して走らせてることは非常に多いですね。
Aプランから逸れる可能性が高ければ別のプランにいくことを考えますし、むしろ、Bプランになる可能性が高いなと思いながら、Aプランを実現するべく努力しつつも、Bプランに移行しやすいように考えて対応しているケースは結構あります。
高確率でBプランの方に移行することを想定しつつAプランで上手くいけば、それはめでたしって話しで、そこは専門家として想定できる事態への抑えをしないといけません。
有事の際に軍資金が尽きて、お手上げになってはいけませんので。
走らせている計画の変更はどのようなきっかけなどがあって検討されるのでしょうか?
それぞれのプランにおいて何が分岐するトリガーなのか把握しておく必要があります。
トリガーのタイミングでプラン変更をしなければいけないこともあれば、総合的に考えてBプランの方が確実に再建できるといった場合は、あえてそのトリガーにヒットさせてプランBにもっていくみたいなことも時には必要で、それをやらないと、ズルズルいって手遅れになりかねないみたいなこともあります。
もちろん、それを仕組んでやったと思われてもいけないみたいな部分は難しいところでもあります。
ただ、経営者自身がその別プランだとかプラン移行のタイミングを考えるのは困難だと思います。
経営者の方は目の前の事業を一生懸命やって、会社の先頭に立ってやっていかないと人は誰もついてきませんので、そういう意味では専門家がそのBプランを考えて準備するというのが重要です。
専門家としては全体としてのバランスを見て冷静に進めるために、今後もし悪くなったらこれが必要ですよねということはどこかでちゃんと理解してもらいます。
ですがまずはAプランで頑張って行こうというところで、ケアというか励ましたり鼓舞したりもします。
そういった際の経営者の方は心身ともに本当に大変だと思います。
- 再生の局面では信頼関係が必須
- 専門家の案件に対する考え方や進め方は洗練されている
関連記事
-

-

-
 2023年09月26日【公認会計士が語る事業再生】企業を「再成長」させることこそが事業再生の本質だ
2023年09月26日【公認会計士が語る事業再生】企業を「再成長」させることこそが事業再生の本質だコロナ禍、人手不足、物価高騰などのざまざまな要因による不況の影響は、多くの企業に対して大きな影響を与...
-