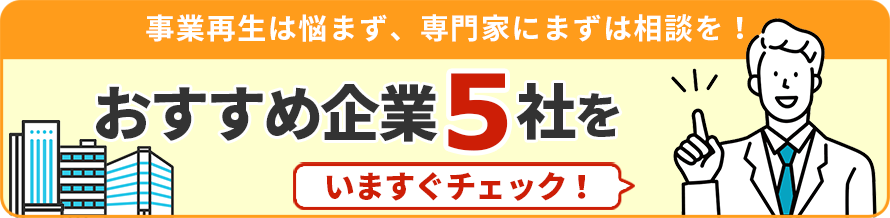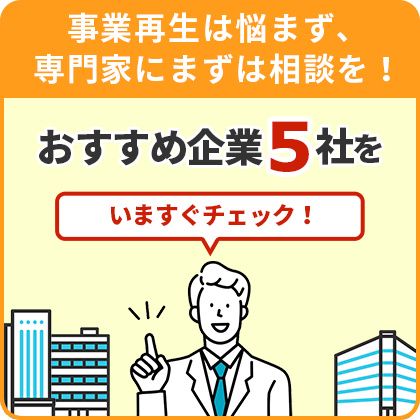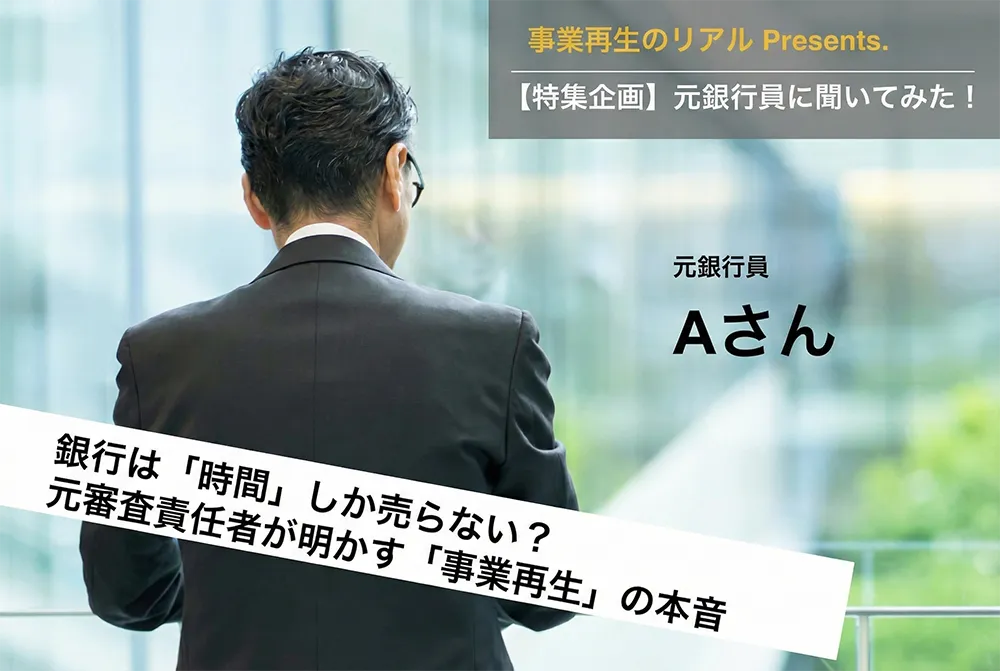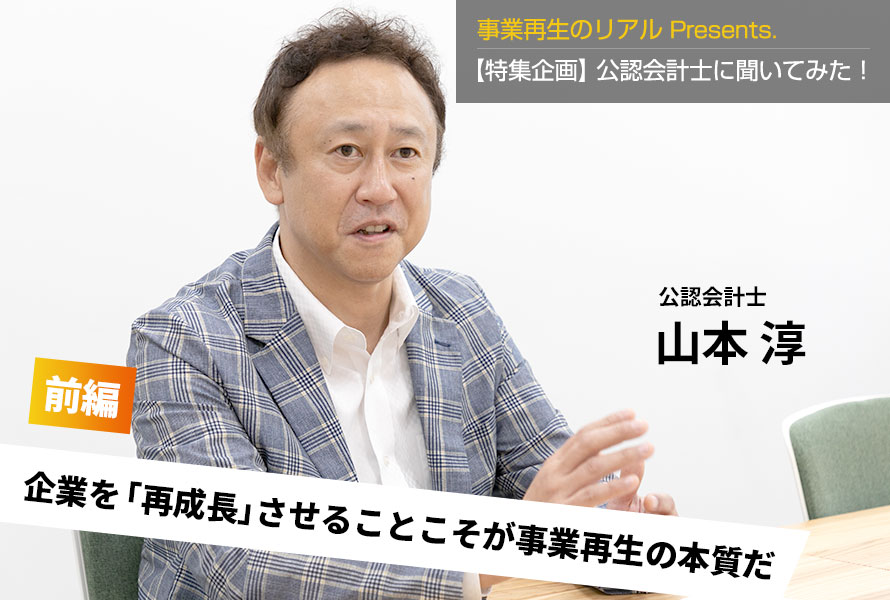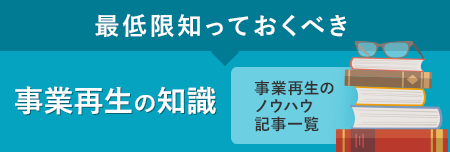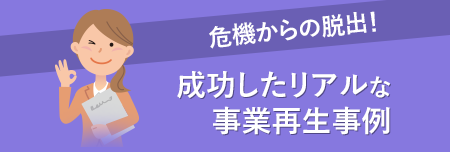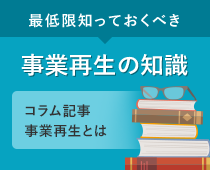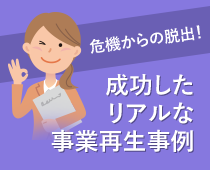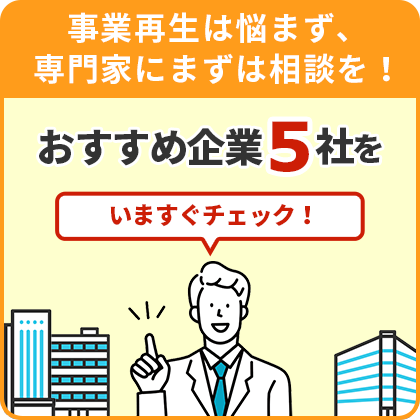2023年06月07日
コロナ禍、人手不足、物価高騰などのざまざまな要因による不況の影響は、企業に対して大きな影響を与えてます。さらに、コロナ禍を乗り切るための「ゼロゼロ融資」も返済が本格化し企業倒産数は3年ぶりに増加しました。(2023年4月現在)
企業の経営に携わっている専門家の多くは、今後、倒産に陥る企業が増加すると予想しています。会社の経営状態が悪化したとき、あるいは悪化する前に倒産という最悪のシナリオを回避して経営の立て直しを図るための方法が「事業再生」です。
今回は、事業承継、M&Aなどの幅広い分野に携わり、これまで100件以上の事業再生案件を遂行してきた弁護士の山崎良太氏(森・濱田松本法律事務所所属)にお話を伺い、事業再生について、経験談を交えながら分かりやすく解説して頂きました。
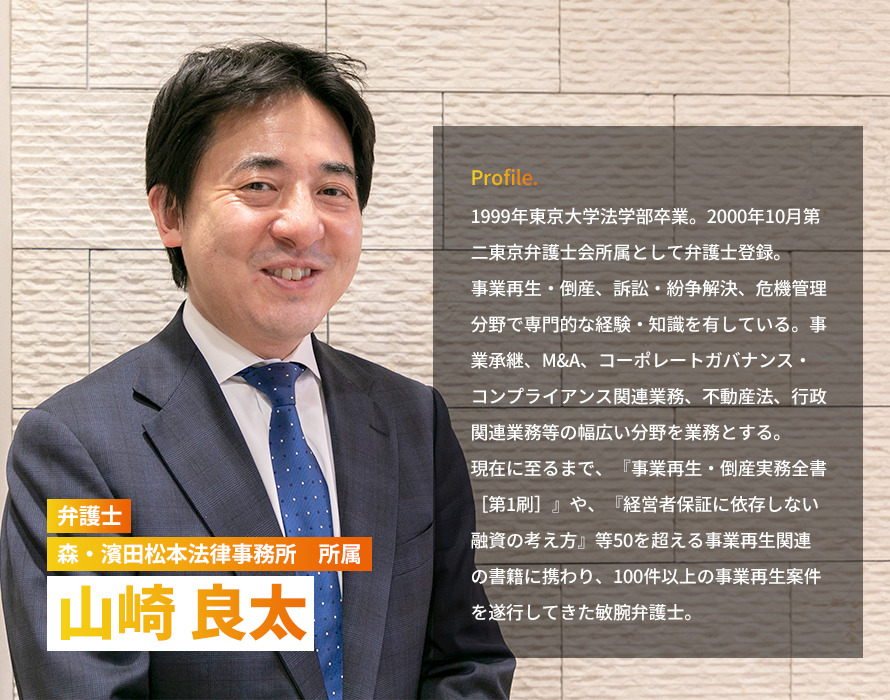
【弁護士が語る事業再生】事業再生の本質とは?
目次 [非表示]
弁護士『山崎良太』のバックボーンとこれまでの実績
-自分の力で人の役に立つ仕事がしたい-
まずは読者の皆さんに対して山崎先生のことをご紹介するというのも兼ねて、山崎先生ご自身の事について伺いたいと思います。
山崎先生が弁護士になることを決めたきっかけや思いなどを教えていただけますか?
弁護士になろうと思ったのは、人のために役に立てる仕事をしたいと思ったという背景があって、単純化するとそういう話なんですよね。
あとは、反骨精神みたいなものが強くあったので、自分が理不尽だと思った時に組織の論理に従って我慢するようなことは無理だと思っていました。そういう理由で、個人事業的な、自分の力でできる仕事で、かつ自分が正しいと思うことや人の役に立つことができる仕事として、弁護士になりたいと決心しました。
ありがとうございます。それでは次に、山崎先生の普段の業務について伺いたいと思います。普段、どのような内容の業務をされていますか?
いろんな仕事をやっています。裁判もしますし、事業再生から、出口としてM&Aまで関わることも多いですね。他には株主総会の指導をやったりとか、いろんな顧問先の法律問題に関してアドバイスをしています。
その中でも特に事業再生の案件に携わっていて、やりがいを感じることを教えていただけますか?
いつも思うのは、経営者の方ってすごく孤独なんですよね。自分の人生だったり家族だったりいろんな思いを背負って経営されてらっしゃるんです。特に再生局面になると、非常にそこがフォーカスされるというか、金融機関も手のひら返したような態度を取ってきたりという場面に直面したとき、当然、社内で相談できる人がいるわけでもないですよね。自分が弱音を言うわけにいかない、という気持ちもあるかもしれない。
そういうときに、具体的に何かをするっていうんじゃなくても、その状況における他のいろんな問題意識だったりとか、その問題をどういうふうに変えて対処していけばいいのかということについて、経営者の方の手助けができるのが私たちの仕事だと思っています。
非常に苦しい局面を迎えている経営者の方の聞き役にもなり、様々な提案をできる役割はいつも担えているなという実感はあります。今苦しい状況にある経営者の方をサポートして、ひいては、事業だったり会社自体であったり、個人であったり、取引先だったり、その守っていくべきものを一緒に守っていくことが、この仕事のやりがいであると感じています。
事業再生といっても様々あると思うのですが、これまで何件の事業再生案件に携わってこられましたか?
現在弁護士歴23年目で、約100件程度です。まさにいろんなステージの事業再生がありましたが、ざっくりそれくらいだと思います。
山崎先生に依頼する会社の企業規模は、どのくらいの規模が多いですか?
年商でいったら10億円とかそれ以上が大半ではあって、再生の仕事は10〜50億円程度の中小企業がボリュームゾーンで、案件数が多いです。
それ以上の大きい規模の企業や上場企業の案件も相当数やっていますが、そもそもそういう規模の会社の再生案件自体が少ないです。もちろん10億円未満の企業もそれなりにありますが、10〜50億円くらいのところが多いですね。
事業再生案件として伴走する期間は、概ねどのぐらいの期間でしょうか?
その会社がどういったスケジュール感でどこを目指して事業再生に取り組んでいくのかにもよりますので、一概には申し上げにくいですが、通常は1年〜2年、長いと3年とか5年ぐらい伴奏したところはあります。
関連記事
-

-

-
 2023年09月26日【公認会計士が語る事業再生】企業を「再成長」させることこそが事業再生の本質だ
2023年09月26日【公認会計士が語る事業再生】企業を「再成長」させることこそが事業再生の本質だコロナ禍、人手不足、物価高騰などのざまざまな要因による不況の影響は、多くの企業に対して大きな影響を与...
-