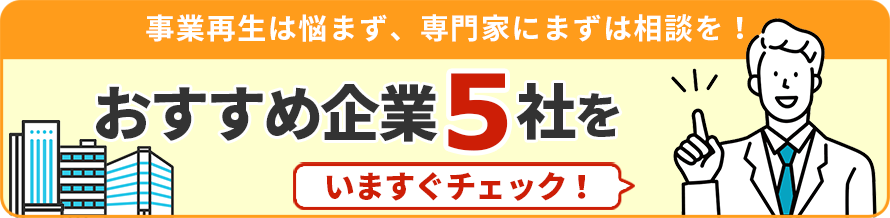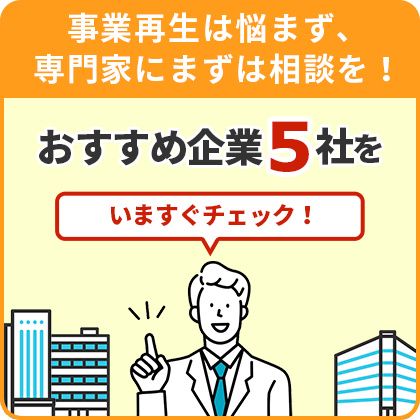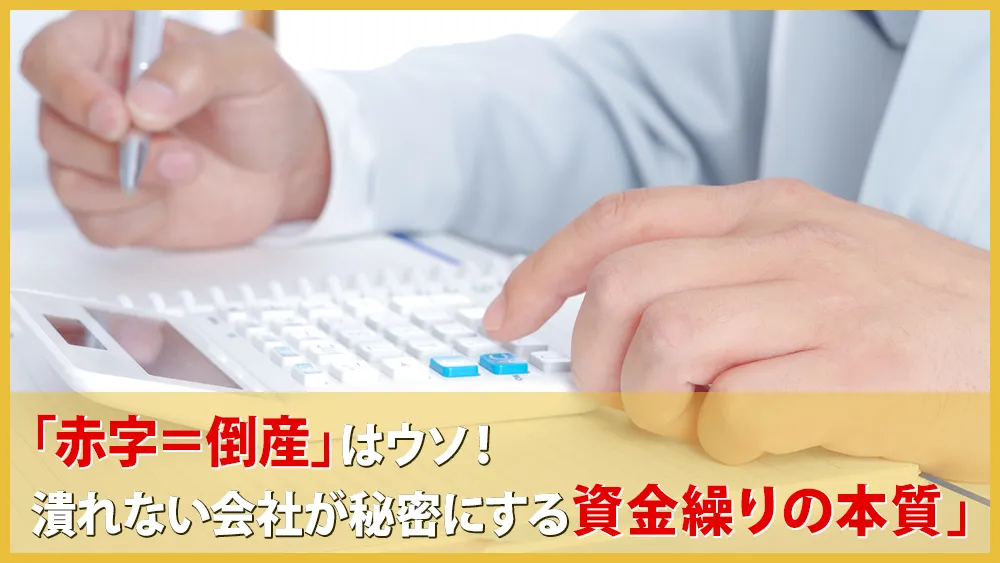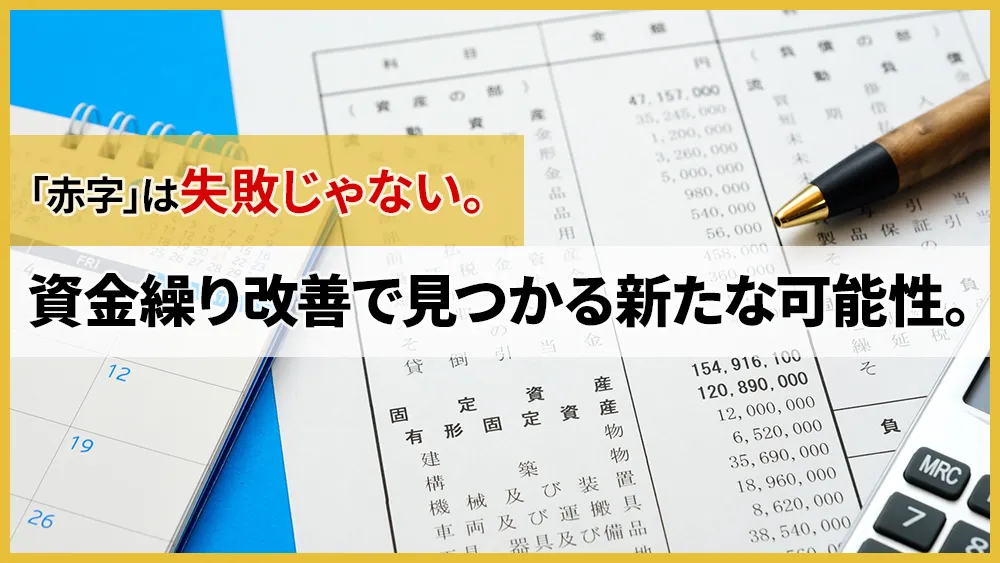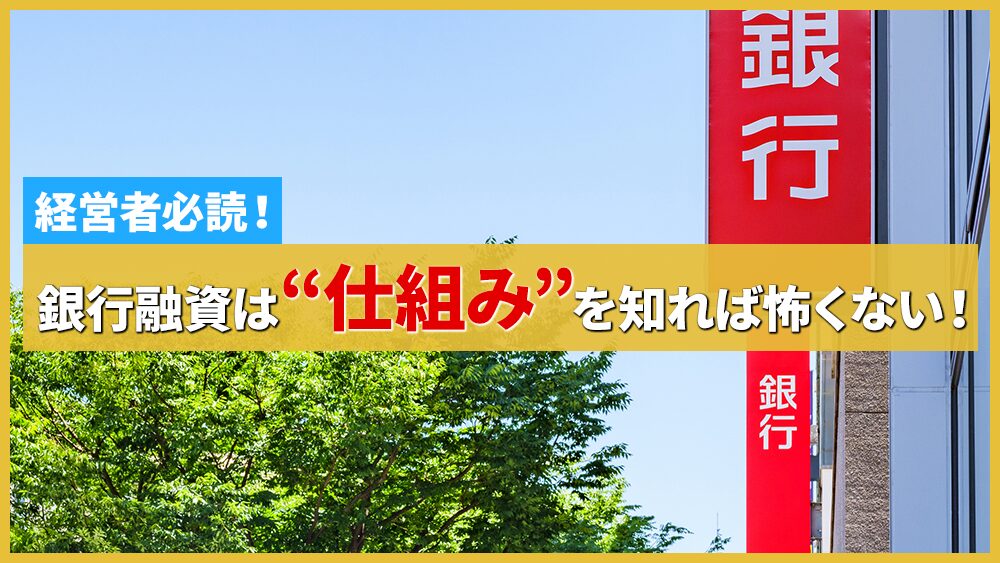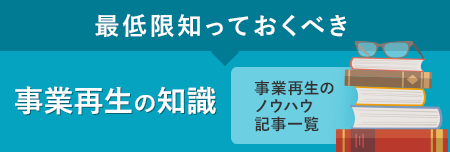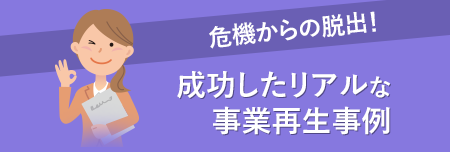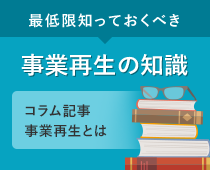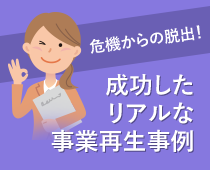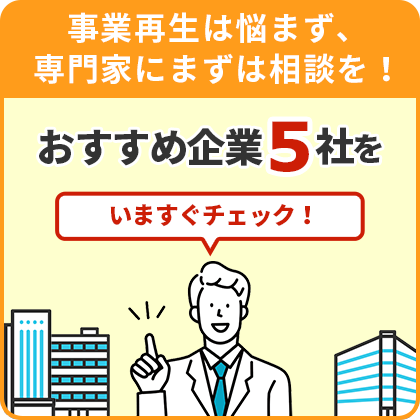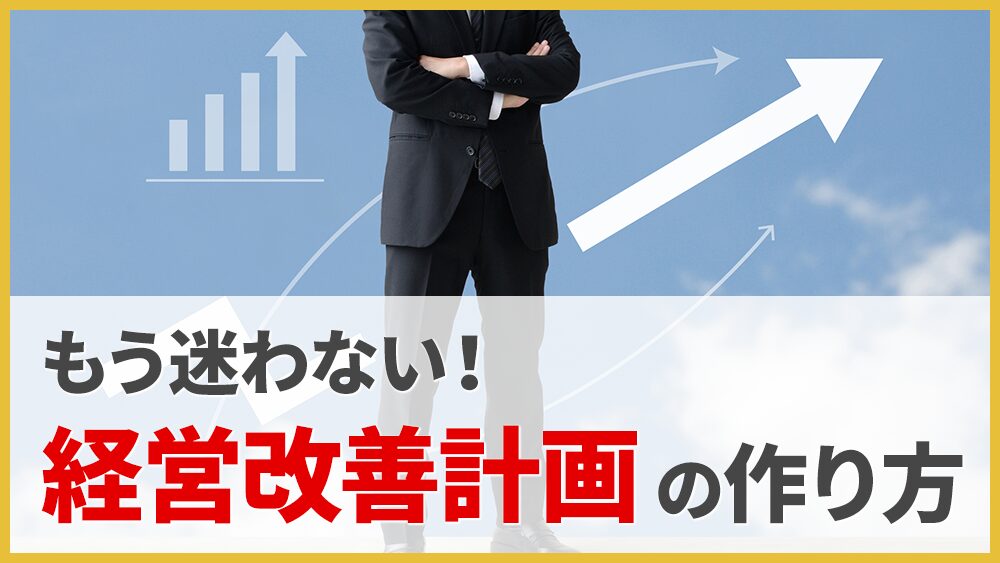
2025年08月29日
経営が厳しくなったとき、ただ延命するのではなく「再生」へと舵を切るために必要なのが「経営改善計画書」です。
金融機関との信頼関係を築き、資金繰りを安定させ、事業の本質的な立て直しを図るためのこの計画書は単なる書類ではなく、企業の未来を左右する戦略ツールと言えます。
本記事では、「経営改善計画 とは」という基本から、作成のタイミング・方法・注意点、そして注目の「405事業」までを、わかりやすく解説します。
目次
この記事で伝えたいこと
経営者に必要な経営改善計画の基礎知識から計画書の作成方法、405事業の最新情報までがわかります。
- 経営改善計画書の目的と作成すべきタイミング
- 記入すべき内容と作成手順を具体的に解説
- 「405事業」とは何か?再生支援の新たな枠組みを理解
経営改善計画とは?経営者が知っておくべき基礎知識
経営改善計画とは、企 業が財務・事業の両面から現状を分析し、課題を明確化したうえで、具体的な改善策と数値目標を盛り込んだ「再生のための設計図」です。
特に中小企業においては、資金繰りの悪化や業績不振が続く局面で、金融機関との信頼関係を再構築し、事業の持続可能性を示すための重要なツールとなります。
この計画は、単なる資金調達のための書類ではなく、経営者自身が自社の現状と向き合い、将来に向けた戦略を描くプロセスそのものです。
次章では、なぜこの計画書が必要なのか、通常の経営計画との違いは何か、そして作成のタイミングや支援先の選び方について、より具体的に解説していきます。
なぜ経営改善計画書が必要なのか
経営改善計画の必要性が本格的に認識され始めたのは、2000年代初頭から中小企業金融円滑化法(2009年施行)の流れを受けたことからです。特にリーマンショック後、資金繰りに苦しむ中小企業が急増し、金融機関との関係を再構築するための「客観的な再生計画」の必要性が高まりました。
その後、経営改善計画は、単なる希望的観測ではなく、実行可能性のある計画が重視されるようになり、「金融支援を受けるための条件」から「企業の持続可能性を示す戦略文書」へと進化してきました。
企業が業績不振や資金繰りの悪化に直面した際、経営改善計画書は再生への第一歩となります。金融機関との信頼関係を再構築し、返済条件の見直しや資金支援を受けるためには、客観的かつ実現可能な改善策を示す必要があるからです。
中小企業庁も「経営改善計画は、企業が自らの課題を認識し、事業の再構築や財務体質の改善を図るために策定する計画」と定義しており、単なる資金調達ではなく、持続可能な経営への道筋を示す戦略文書として位置づけられています
経営計画と経営改善計画の違い
経営改善計画と混同されやすいものに、経営計画があります。いずれも企業の将来を見据えた戦略文書ですが、目的と前提条件が大きく異なります。
以下に、経営計画と経営改善計画の違いを一覧表で比較しました。
| 比較項目 | 経営計画 | 経営改善計画 |
|---|---|---|
| 目的 | 成長・拡大・新規展開 | 再生・立て直し・金融支援の獲得 |
| 前提 | 財務健全・黒字基調 | 業績不振・資金繰り悪化・債務超過など |
| 内容 | 市場拡大・投資計画・人材戦略 | 課題分析・改善策・資金繰り計画・返済計画 |
| 対象 | 社内・投資家・取引先 | 金融機関・支援機関・社内 |
| 支援制度 | 通常の補助金・助成金 | 405事業・再生支援協議会など |
経営計画は通常の成長・拡大を目指す「攻めの計画」であり、健全な財務状況を前提に策定されます。一方、経営改善計画は業績不振や資金繰りの悪化など「再生が必要な状況」において、課題の解決と財務体質の立て直しを目的とする「守りと再構築の計画」です。
いつ経営改善計画書を作成すべき?
経営改善計画書は、企業が財務的・事業的に危機的状況にあるとき、早期に作成すべきです。特に資金繰りの悪化や債務超過が顕在化する前に、現状を整理し、金融機関との対話を始めることが重要です。中小企業庁も「早期の計画策定が再生の可能性を高める」としています。
下記のような兆候が見られた場合は、速やかな作成が推奨されます。
- 毎月の資金繰りが不安定で、借入返済が困難になりつつある
- 売上が継続的に減少し、赤字が続いている
- 金融機関から「経営改善の必要性」を指摘された
- 債務超過や税・社会保険料の滞納が発生している
- 主要取引先の喪失などで事業継続に不安がある
こうした状況では、計画書を通じて課題を明確化し、支援制度や専門家の力を借りながら再生の道筋を描くことが求められます。
どこの誰に作成を依頼したら良いか
経営改善計画書は、経営者自身が作成することも可能ですが、財務分析や数値計画、金融機関との交渉を伴うため、専門的な知識が求められます。
実務上は、税理士・中小企業診断士・公認会計士などの専門家に依頼するのが一般的ですが、「認定経営革新等支援機関」に登録された事業再生コンサルティング事務所への依頼が特におすすめです。
事業再生コンサルタントなら、計画策定から金融機関との交渉、公的支援制度を活用しながらの実行支援まで一貫したサポートを受けられます。信頼できる専門家との連携が、再生成功の鍵となります。
経営改善計画書の作成方法と記載内容
 経営改善計画書は、企業の現状分析から改善策の立案、数値計画の策定までを体系的にまとめた再生のための戦略文書です。金融機関との交渉や支援制度の活用において不可欠であり、実現可能性と継続性が求められます。
経営改善計画書は、企業の現状分析から改善策の立案、数値計画の策定までを体系的にまとめた再生のための戦略文書です。金融機関との交渉や支援制度の活用において不可欠であり、実現可能性と継続性が求められます。
以降の記事では、計画書の基本構成、作成手順、そして成功のためのポイントについて具体的に解説します。
基本構成と記載項目
経営改善計画書は、企業の再生に向けた課題整理と改善策を体系的に示す文書です。金融機関との交渉や支援制度の活用において、以下のような構成が一般的です。
- 現状分析:財務状況、事業構造、市場環境
- 経営課題と改善方針:課題の抽出と対応方針
- アクションプラン:具体的な改善施策と実行体制
- 数値計画:損益予測、資金繰り表、BS改善計画
- 金融支援内容:返済条件変更や追加融資の要望
中小企業庁では、「経営改善計画の事例サンプル」を用意していますので、経営改善計画策定支援のページからダウンロードできます。また、「資金予定表かんたん作成ツール」や「早期経営改善計画 ひな形」なども、早期経営改善計画策定支援のページからダウンロード可能です。
作成の流れとステップ
経営改善計画書の作成は、現状の把握から改善策の立案、数値計画の策定、金融機関との協議まで段階的に進める必要があります。特に初期段階での課題抽出と、実現可能な改善策の設計が成功の鍵です。
以下は、一般的な作成ステップを示したフローチャートです。
| フロー | 内容 |
|---|---|
| ①現状分析 | 財務・事業・市場の把握 |
| ②課題の抽出 | 赤字要因・資金繰りの問題など |
| ③改善策の立案 | コスト削減・収益改善・組織改革 |
| ④数値計画の策定 | 損益予測・資金繰り表・BS改善 |
| ⑤実行体制 | 役割分担・モニタリング方法 |
| ⑥金融機関との協議 | 返済条件変更・支援要請 |
専門家と連携しながら計画を練り上げることで、金融機関からの信頼を得やすくなり、再生支援制度の活用にもつながります。
作成時の注意点と成功のコツ
経営改善計画書の作成にあたっては、金融機関や支援機関が納得できる「実現可能性」と「継続性」が重要です。単なる希望的観測ではなく、根拠ある数値と具体的な改善策を盛り込むことが成功の鍵となります。
以下に注意点と成功のコツを、一覧表で具体的に示してみましょう。
| チェック欄 | 項目 | 内容 |
|---|---|---|
| 実現可能性 | 過去実績や市場環境に基づいた現実的な数値計画を立てる | |
| 客観性 | 第三者(専門家)のレビューを受けて信頼性を高める | |
| 継続性 | 実行体制やモニタリング方法を明示し、計画倒れを防ぐ | |
| 金融機関との対話 | 事前協議を行い、計画内容に対する理解と合意を得る | |
| 書式の整備 | 中小企業庁や支援機関のテンプレートを活用し、形式を整える |
これらを意識することで、計画書が単なる書類ではなく、再生への実効性あるツールとなります。
「405事業」とは?経営改善支援の新たな枠組み
 「405事業(経営改善計画策定支援事業)」とは、中小企業庁が推進する経営改善支援制度で、業績不振や資金繰りに課題を抱える企業が専門家の支援を受けながら経営改善計画を策定・実行できる枠組みです。
「405事業(経営改善計画策定支援事業)」とは、中小企業庁が推進する経営改善支援制度で、業績不振や資金繰りに課題を抱える企業が専門家の支援を受けながら経営改善計画を策定・実行できる枠組みです。
計画策定費用やモニタリング費用の補助が受けられ、金融機関との連携を通じて事業再生を図ることが目的です。
以降のコラム記事では、その概要・対象・活用メリットについて詳しく解説します。
405事業の概要と目的
405事業は、財務上の課題を抱える中小企業が専門家の支援を受けながら、実現可能な経営改善計画を策定できるよう国が補助する制度です。
制度名の「405」は、創設当初の予算額405億円に由来します。背景には、リーマンショック後の資金繰り悪化や、ゼロゼロ融資の返済期到来による再生ニーズの高まりがありました。
目的は、認定支援機関・金融機関・企業の三者連携により、計画策定と金融支援を一体的に進め、事業再生を促すことにあります。
対象企業と支援内容
405事業の対象となるのは、財務上の課題を抱え、自力で経営改善計画を策定することが困難な中小企業・小規模事業者です。
資金繰りの不安や借入金の返済負担が重く、金融機関との関係構築が必要な企業が主な対象です。支援内容は、計画策定から実行支援(伴走支援)まで多岐にわたります。
▼対象企業の主な条件
- 借入金の返済負担など財務上の問題を抱えている
- 自社で経営改善計画を策定することが難しい
- 金融機関からの支援(リスケ、借換など)が見込まれる
▼支援内容一覧
| 支援項目 | 内容 | 補助率・上限 |
|---|---|---|
| DD(デューデリジェンス)・計画策定支援 | 財務・事業分析と改善計画の策定 | 2/3(上限200万円) |
| 伴走支援(モニタリング) | 計画実行の支援・進捗管理 | 2/3(上限100万円) |
| 金融機関交渉支援 | 経営者保証解除等の交渉支援 | 2/3(上限10万円) |
これらの支援は、認定経営革新等支援機関(事業再生コンサルタント・税理士・中小企業診断士など)を通じて受けることができ、費用の2/3が補助されるため、企業の負担を大きく軽減できます。
※詳細は中小企業庁の公式ページをご参照ください。
405事業を活用するメリット
405事業を活用することで、経営改善計画の策定や実行における負担を大幅に軽減できます。専門家の支援を受けながら、金融機関との交渉を円滑に進めることができ、再生の可能性を高めるという実効的なメリットがあります。
以下に、主な利点を一覧表で示します。
| メリット | 内容 |
|---|---|
| 費用負担の軽減 | 計画策定・モニタリング費用の2/3補助(最大300万円) |
| 専門家の支援 | 認定支援機関による財務分析・改善策の立案支援 |
| 金融機関との連携強化 | バンクミーティングの調整や返済条件変更の交渉支援 |
| 計画の実現性向上 | 客観的な視点で計画の精度と信頼性が高まる |
| 継続的な伴走支援 | 計画実行後も3年間のモニタリング支援が受けられる |
これらの支援を通じて、経営者は再生に向けた具体的な道筋を描きやすくなり、金融機関との信頼関係も構築しやすくなります。制度の活用は、単なる資金対策ではなく、事業の持続可能性を高める戦略的選択です。
経営改善計画に関するよくあるご質問にお答えします
Q経営改善計画書は自社だけで作成できますか?
A可能ですが、財務分析や数値計画の精度が求められるため、専門家の支援を受ける方が金融機関の理解を得やすく、計画の実現性も高まります。
Q事業再生コンサルタントに依頼するメリットは何ですか?
A財務・事業両面の課題を客観的に整理し、実現可能な改善策を構築できます。金融機関との交渉支援や405事業の補助申請も代行してもらえるため、再生成功率が高まります。
Q経営改善計画書はどのタイミングで提出すべきですか?
A資金繰りが不安定になった時点で早期に作成・提出するのが理想です。金融機関からの要請があった場合は、速やかに対応しましょう。
Q計画書に記載する数値はどの程度の精度が必要ですか?
A過去実績や市場環境に基づいた根拠ある予測が必要です。希望的観測ではなく、実行可能性を重視した数値計画が求められます。
Q405事業の補助を受けるにはどうすればよいですか?
A認定経営革新等支援機関(事業再生コンサルタント・税理士・診断士など)を通じて申請します。中小企業庁の公式サイトに申請様式と手順が掲載されています。
まとめ:経営改善計画は「再生の設計図」
経営改善計画は、単なる資金繰り対策ではなく、企業の再生を実現するための「設計図」です。財務・事業の両面から課題を明確にし、実行可能な改善策と数値計画を示すことで、金融機関との信頼関係を再構築し、持続可能な経営へと導くことができます。
本コラムでは、経営改善計画の基本的な考え方から、作成のタイミング、支援を受けるべき専門家の選び方、そして「405事業」の活用方法まで、実務に役立つ情報を体系的に解説しました。特に、計画書の精度と実行力を高めるためには、専門家との連携が不可欠です。
当サイトがおすすめする事業再生に強いコンサル会社は、いずれも認定経営革新等支援機関です。そのため、405事業の補助制度を活用しながら、計画策定から金融機関との交渉、実行支援まで一貫したサポートを受けることが可能です。
経営に不安を感じたときこそ、早期の対応が再生への第一歩です。信頼できる支援者とともに、未来を描く経営改善計画を始めてみませんか。
関連記事
-

-
 2025年09月24日資金繰りが厳しい…手遅れになる前の選択肢とは?赤字からの再生戦略と資金調達
2025年09月24日資金繰りが厳しい…手遅れになる前の選択肢とは?赤字からの再生戦略と資金調達資金繰りが厳しい…このままでは手遅れかもしれない。そんな不安を抱える経営者の方へ。赤字が出ていても、...
-

-

-