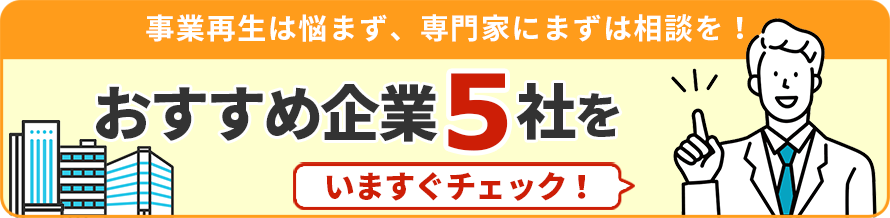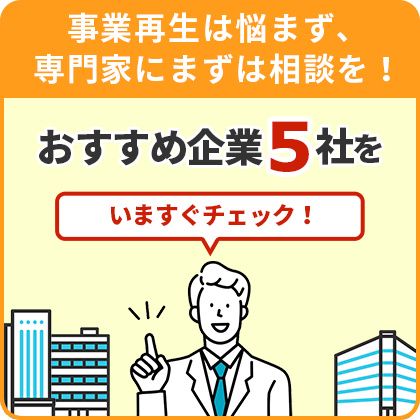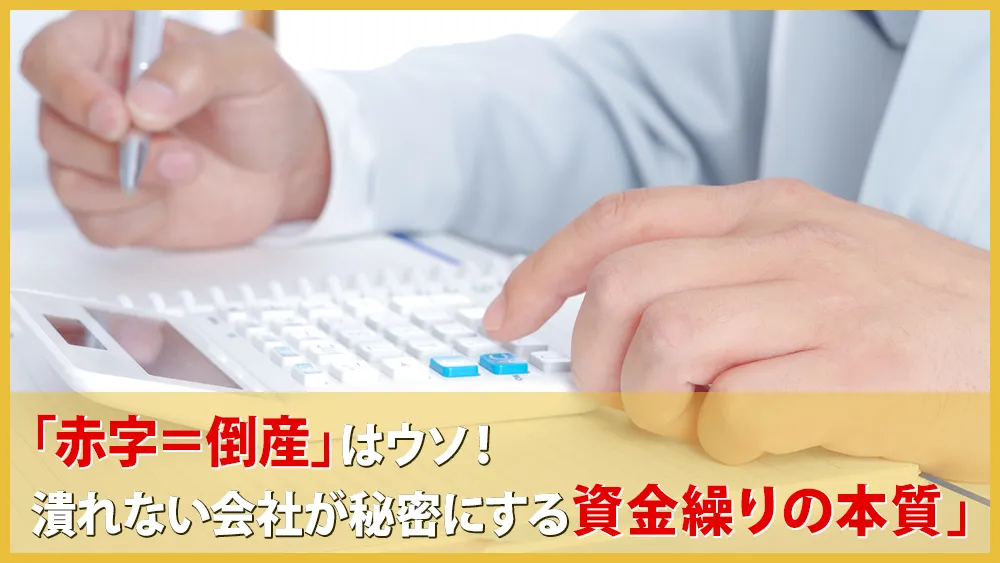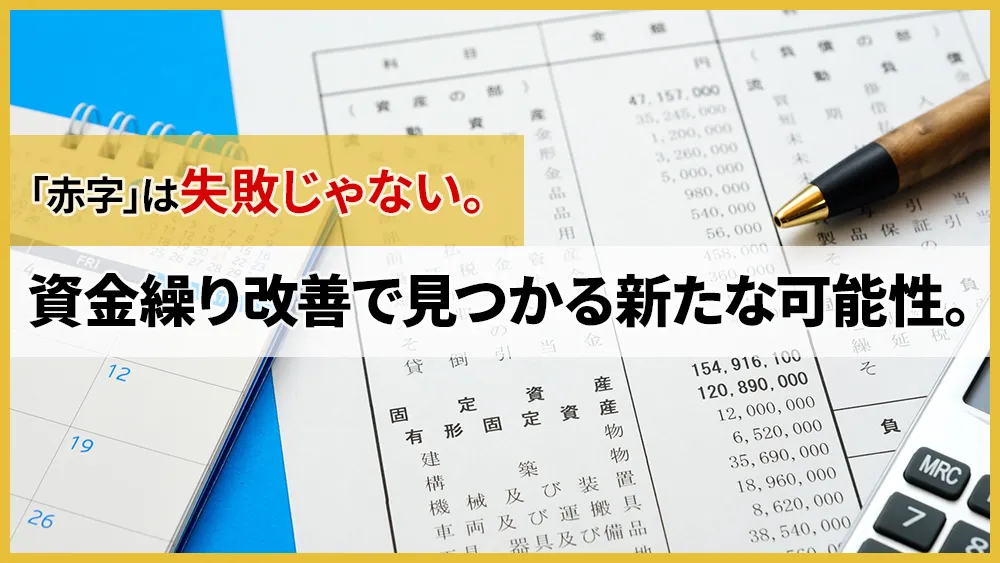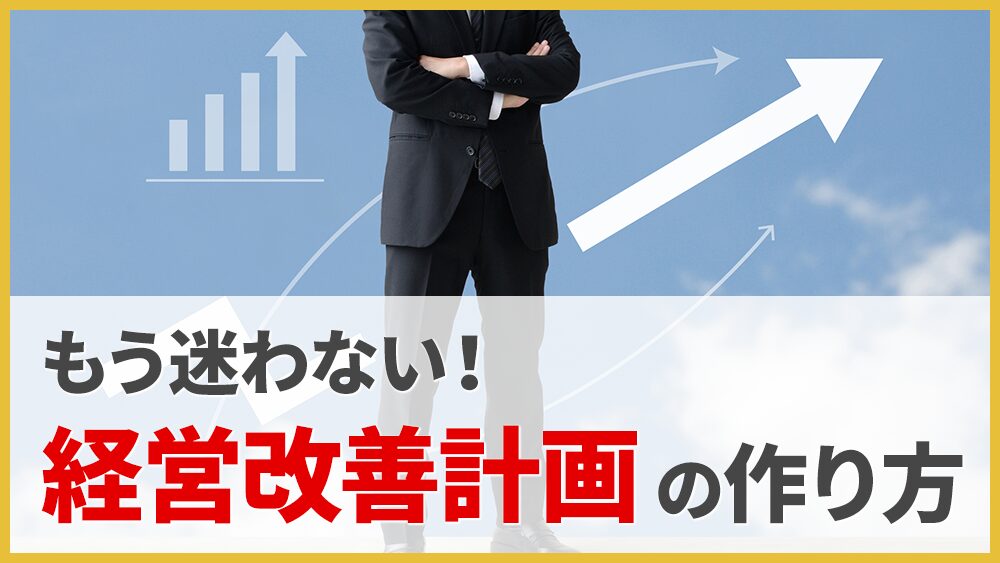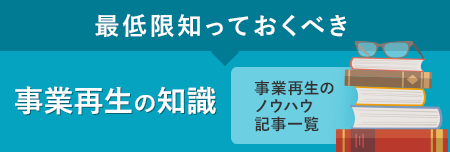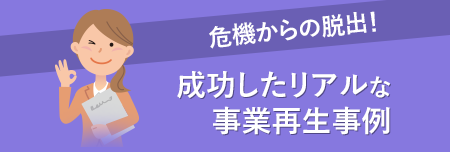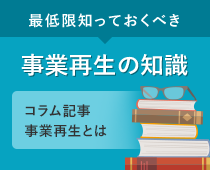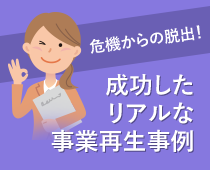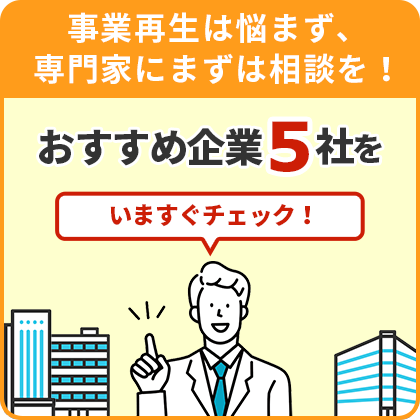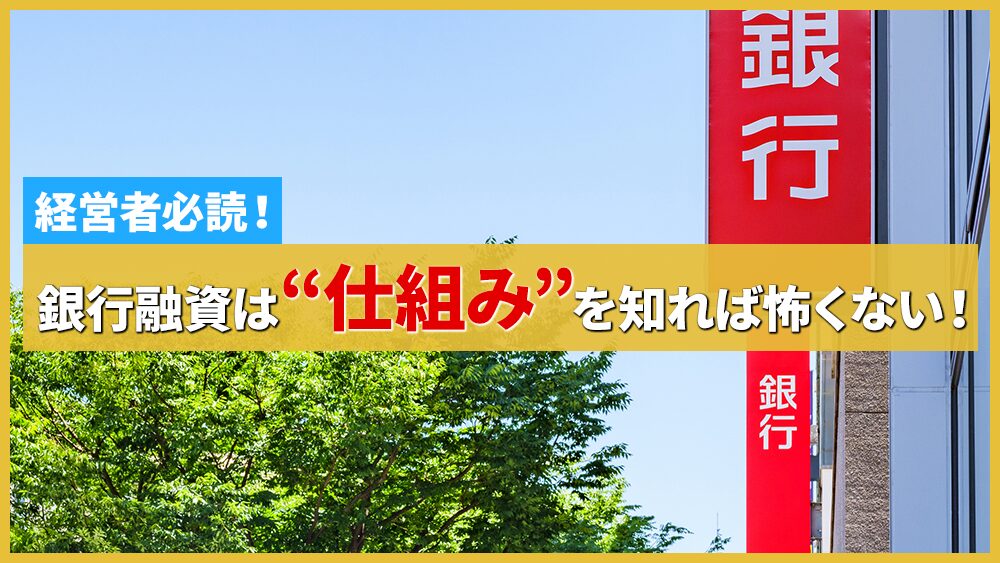
2025年08月29日
銀行融資を受ける際に「どう審査されるのか」「何を準備すればいいのか分からない」と不安を抱かれる経営者の方も多いでしょう。審査の仕組みを知らずに融資を申し込むのは、地図なしで山登りするのと同じです。逆にいえば、融資審査の仕組みを事前にしっかり理解しておくことで、資金調達の成功率は格段にアップします。
この記事では、審査の流れや落ちる主な理由、通過するためのポイントまで、わかりやすく徹底解説します。
銀行融資の審査を過度に不安になる必要はありません。この記事では審査の流れや落ちる理由、通過するための具体策など、「これだけ知っておけば大丈夫」という内容を盛り込んでいます。まずは正しく知り、着実に準備を始めましょう。
目次
銀行融資の基礎知識
 「銀行融資って難しそう」と感じていませんか?このパートでは銀行融資の審査の仕組みについてわかりやすく解説します。基本がわかれば、はじめてでも安心して申し込みの一歩が踏み出せます。
「銀行融資って難しそう」と感じていませんか?このパートでは銀行融資の審査の仕組みについてわかりやすく解説します。基本がわかれば、はじめてでも安心して申し込みの一歩が踏み出せます。
銀行融資とは何か
銀行融資とは、銀行が企業や個人事業主に対して「事業資金」を貸し出す制度です。法人だけでなく個人事業主も対象となるため、事業規模に関わらず多くの事業者にとって強い切り札となります。
「自分の会社も借りられるのか?」とご不安な方もご安心ください。しっかりと準備すれば、銀行融資を利用できる可能性は十分にあります。
他の資金調達方法との違い
銀行融資は、クラウドファンディングやビジネスローン、リース契約など他の資金調達方法と比べても、低金利でかつ大きな額を調達しやすいのが大きな特徴です。その一方で、審査に時間がかかる・提出書類が多いという側面もあります。ただし審査基準と仕組みを理解して対策すれば、もっとも安定した資金調達手段となるでしょう。
銀行融資の種類
銀行の融資には、主に以下のような種類があります。
| 種類 | 特徴 |
|---|---|
| プロパー融資 | 保証協会を介さず、銀行が直接リスクをとる融資。信用力が高い企業向け。 |
| 信用保証付融資 | 信用保証協会が保証人となることで、比較的信用力の低い企業も利用しやすい。 |
| 不動産担保融資 | 所有する不動産を担保に資金調達が可能。担保評価によって融資額が決定。 |
| 制度融資 | 自治体や国の制度を活用した低利の融資。地域の中小企業を支援する目的が強い。 |
| 売掛債権担保融資 | 売掛金(売上債権)を担保にして資金を借りられる。 |
| カードローン/ビジネスローン | スピーディな審査・少額の資金調達に向く。ただし、金利は高め。 |
自社の状況に応じて最適な融資種類を選びましょう。
銀行融資の審査の仕組み
 ここからいよいよ本題、銀行融資の審査の仕組みについて詳しく解説します。「どうせ落とされる…」とあきらめるのはまだ早い。“審査の裏側”を知ることが資金調達への第一歩です。
ここからいよいよ本題、銀行融資の審査の仕組みについて詳しく解説します。「どうせ落とされる…」とあきらめるのはまだ早い。“審査の裏側”を知ることが資金調達への第一歩です。
銀行融資審査の目的
そもそもなぜ銀行融資には厳格な審査があるのでしょうか?銀行は預かったお金を融資として貸し出しているため、貸し倒れは絶対に避けなければなりません。
融資を申し込んだ人に返済能力があるか、事業の継続性は十分か、信用に値するかを見極めるのが審査の最大の目的です。
たとえば、友人や知人が「お金を貸してほしい」と言ってきても、まずはその人が確実に返してくれるかどうかをよくよく考えるかと思いますが、それと同じです。
銀行内での審査フロー
銀行の審査は1人の担当者だけで決まるわけではありません。以下のような流れがあります。
- 1.窓口またはウェブで申し込み
- 2.担当者が書類・内容を精査し、支店長へ報告
- 3.支店長や融資責任者が内容を再確認
- 4.本部の審査部門で最終判断
申込内容や申込者の情報は複数の目で確認されるため、主観的な印象だけで審査が決まることはありません。「どのような点に着目されるのか?」を理解することで、対策も練りやすくなります。
審査時に評価される主な項目
銀行融資の審査項目は明確に公表されているわけではありませんが、主に下記が重視されます。
- 1.財務状況(売上・利益・負債)
- 2.担保や保証人の有無
- 3.過去の返済履歴・信用情報
- 4.事業の将来性や計画の具体性
これらがシビアに見られていることを意識して、審査に臨むことが重要です。
銀行融資の流れ
 銀行融資は低金利・大きな融資枠が魅力な反面、申込から入金までいくつものステップがあります。しかし、一つ一つ理解しておけば審査も落ち着いて対応できますので、安心して進めていきましょう。
銀行融資は低金利・大きな融資枠が魅力な反面、申込から入金までいくつものステップがあります。しかし、一つ一つ理解しておけば審査も落ち着いて対応できますので、安心して進めていきましょう。
事前相談・申し込み
銀行融資は窓口やウェブサイトからの申し込みが基本ですが、不安な場合は事前に窓口で相談も可能です。「融資について相談したい」と一言伝えれば、丁寧に説明してもらえるので、初めてでも気軽に一歩を踏み出せます。
必要書類の準備
| 基本書類 | ・企業の登記事項証明書 ・基本規約 ・会社案内、パンフレット、製品・サービスカタログ ・事業プラン書類 |
|---|---|
| 財務関連書類 | ・決算書(過去3期分以上) ・税務申告時の書類一式 ・合計残高試算表(決算後3ヵ月以上過ぎている場合) ・キャッシュフロー表 |
| 本人確認書類(代表者のもの) | ・マイナンバーカードor運転免許証orパスポートのコピー ・印鑑証明 |
| その他 | ・設備投資の見積書 ・担保物件の登記事項証明書 ・納税額を証明する書類 など |
融資には多くの書類が必要です。主に基本書類、財務関連書類、代表者の本人確認書類、その他(担保に関するものなど)が挙げられます。お金に関する書類は特に厳しくチェックされるため、抜け・漏れのないよう細心の注意が必要です。
面談・ヒアリング
提出書類に基づき、銀行担当者と面談やヒアリングが実施されます。銀行員が直接会社に来る場合もあり、事業内容や資金の使い道を細かく確認されます。準備した書類の内容と整合性が取れた説明ができるよう、シミュレーションしておくと安心です。
審査
書類の確認・面談が終わると本格的な審査に入ります。審査には1か月前後かかることが多く、早めの準備が重要です。審査期間も見越した資金計画を立てましょう。
融資契約・入金
審査が無事に通れば、融資契約の締結と入金が行われます。契約内容は慎重に確認し、疑問点は必ず事前に解消してから進めましょう。入金後は、計画通りの資金使途を守り、しっかりと返済していくことが、今後の融資にも好影響をもたらします。
銀行融資が通らない主な理由7つ
いくら正しく申し込み手続きを踏んでも、残念ながら審査に落ちてしまうこともあります。その主な理由を見ていきましょう。自社が該当しないか今のうちにチェックしておくことが大切です。
信用情報に傷がある
過去の返済遅延や金融事故が信用情報に記録されていると、銀行は貸し渋る傾向が強まります。「この会社は本当に信頼できるか?」という視点で厳しく見られるため、信用情報はしっかり確認しておきましょう。
財務状況が赤字や債務超過
決算書が赤字である、債務超過に陥っていると、銀行は「返済できる見込みが薄い」と判断しやすいです。たとえ一時的な赤字でも、その理由や今後の改善計画を明確に説明できることが求められます。
他の借入残高が多い
すでに他行やノンバンクから多額の借入がある場合、「返済負担が大きすぎる」とみなされ、審査が厳しくなります。特に高金利の借入が多いと、資金繰りへの不安が高まるため注意が必要です。
税金・社会保険を滞納している
納税証明書や決算書で税金や社会保険料の滞納が推察されると、返済能力に疑問符がつき、審査でNGとなりやすいです。滞納分は審査前に必ず支払っておきましょう。
事業計画が具体性に欠ける
銀行は「融資した資金がどのように使われるか」をもっとも重視しています。事業計画に具体性や現実性がないと、「本当に返済原資を生み出せるのか?」と不安視されます。
申込前には、書類・面談の両面で「いつ」「どの事業で」「どう資金を使うか」を説得力ある言葉で伝えられるよう準備しましょう。
自己資金が少ない
自己資金の乏しさも審査落ちの大きな要因です。銀行側は「自分のお金をほとんど使わずに借金頼みでは、事業継続も融資返済も厳しいのでは」と判断しがちです。
日本政策金融公庫の調査では「創業資金のうち自己資金の割合が24%未満だと審査通過が難しい」としており、一定割合以上の自己資金を用意できているかも重要です。
担保や保証人が用意できない
企業向けの銀行融資では、担保や保証人を求められるケースが一般的です。万が一返済不能になった場合のリスクヘッジ策となるため、用意できない場合は、保証協会を利用した融資(信用保証付融資)を検討しましょう。個人事業主でもこの枠組みを活用できます。
銀行融資を通すためのポイント
 ここまで読んで「自社も条件をクリアできるだろうか?」と不安に思われた方も多いかもしれません。しかし、時間をかけて着実に準備すれば、銀行融資の審査を突破できる可能性は比較的高くなります。ここからは審査を通すためのポイントをまとめますので、ぜひ一つずつチェックしてください。
ここまで読んで「自社も条件をクリアできるだろうか?」と不安に思われた方も多いかもしれません。しかし、時間をかけて着実に準備すれば、銀行融資の審査を突破できる可能性は比較的高くなります。ここからは審査を通すためのポイントをまとめますので、ぜひ一つずつチェックしてください。
きちんとした事業計画書を作る
事業計画書は融資の可否を分ける重要書類です。計画書には、「なぜ今この資金が必要なのか」「資金をどのように使い、いつまでにどのような成果を出すのか」「返済原資はどの事業・キャッシュフローから生まれるのか」を明確に記載しましょう。数字や根拠がはっきりした計画で、銀行担当者の疑問にすべて答えられることが理想です。
決算書を改善する
決算書は「会社の健康診断書」ともいえます。
- 資産・負債・利益の推移
- 経常利益や営業キャッシュフローが黒字か
- 適切な資金繰りがなされているか
これらのポイントが分かる書類内容になっているか見直しましょう。仮に赤字が続いている場合はその理由と改善計画を別紙で説明するのも有効です。可能であれば専門家のチェックも受けてみてください。
担保や保証人の準備
担保や保証人は銀行にとっては大きな安心材料です。自社で用意できる不動産や頼れる保証人がいる場合は、極力そろえる努力をしましょう。
どうしても難しい場合は、信用保証協会や他の制度融資枠の利用も検討することが大切です。
税金・社会保険料を期限内に納付
税金や社会保険料は、銀行審査で必ずチェックされるポイントです。一度滞納してしまっても、審査前に納付を済ませ、延滞がない状態で臨むことが重要です。「払っていないのでは?」と思われると致命的なので、日頃から管理を徹底しましょう。
銀行との関係構築
銀行との信頼関係は、一朝一夕には築けません。日頃から定期的な情報共有や相談を心がけ、経営の透明性・誠実さをアピールすることが大切です。小さなことでもマメな連絡を重ねることで、いざというときにスムーズな対応をしてもらえます。
自己資金の確保
事業拡大や経営維持のためには、融資だけでなく自己資金の確保も不可欠です。借入と自分の資金をバランス良く組み合わせることで、銀行からの信用度もアップします。日々の経費管理・利益確保に努め、自己資金比率を少しずつでも高めていきましょう。
審査に落ちた場合の対応策。再チャレンジに向けて
 万が一審査に落ちても、そこで終わりではありません。リスクヘッジのためにも、「ダメだった場合の対応策」を知っておくことで、落ち着いて再チャレンジへの準備ができます。原因の見直しと対策を重ねれば、資金調達の道は必ず開けます。
万が一審査に落ちても、そこで終わりではありません。リスクヘッジのためにも、「ダメだった場合の対応策」を知っておくことで、落ち着いて再チャレンジへの準備ができます。原因の見直しと対策を重ねれば、資金調達の道は必ず開けます。
審査に落ちた理由を考える
まずは「なぜ審査に通らなかったのか」を分析することが重要です。税金や支払いの遅延、財務的な問題、事業計画の甘さなど、課題を洗い出し、改善できるポイントから着手しましょう。場合によっては資金調達方法の再検討も有効です
銀行からフィードバックを得る
可能な場合は、銀行担当者に「どこがダメだったのか」「どのような改善をすればいいか」フィードバックを求めましょう。改善策が明確になるだけでなく、誠意ある姿勢を見せることも次回申込時のプラス材料になります。
他の金融機関や公的融資の活用を検討
ひとつの銀行でNGでも、他の金融機関や公的融資制度に目を向けてみましょう。銀行によって審査基準や重視点が異なることもあるため、複数行・複数制度を比較検討するのも有効です。ただし、どの金融機関でも繰り返し落ちる場合は自社の改善ポイントを見直す必要があります。
時間をおいて再チャレンジ
理由がクリアになり、必要な改善策を実行した上で少し時間を置いてから再度同じ銀行へ申し込むのも選択肢のひとつです。急ぎでなければ、財務改善や信用情報の回復を待って、万全の状態で再チャレンジしましょう。
【Q&A】銀行融資の審査仕組みについて、よくあるご質問
ここからは経営者からよく寄せられる銀行融資の審査に関するご質問にお答えします。知っておくと安心できるポイントをまとめました。
Q銀行融資の審査はどれくらいの期間で結果が出ますか?
A一般的には1か月前後が目安ですが、審査内容や案件の難易度によっては2か月程度かかる場合もあります。また、必要書類の不備や追加資料の提出要請が発生すると、さらに期間が延びることもあるので、早め早めの準備・申し込みを心がけましょう。
なお、制度融資や保証協会付き融資の場合は、自治体や協会の審査をはさむため、より長期化することもあります。
Q赤字決算でも銀行融資を受けられますか?
A赤字決算でも絶対に融資NGというわけではありません。一時的な赤字であることが証明できる、経常利益が黒字、担保や保証人の存在など、「他の安心材料」があれば審査を通過できる可能性があります。
逆に、赤字の原因が不明瞭な場合や債務超過が続いている場合は、厳しくチェックされます。しっかりとした説明と今後の改善計画を用意しましょう。
Q融資審査で最も重視されるポイントは何ですか?
A銀行が最も重視するのは「貸したお金が確実に返ってくるかどうか」です。そのため、決算書や事業計画、返済履歴、担保や保証人の有無などを総合的に評価します。
特に過去の返済実績、今後の事業の安定性、具体的な返済原資が明確であればあるほど、審査通過の可能性は高まります。提出書類は正確・誠実に記載しましょう。
【まとめ】仕組みを理解すれば、銀行融資成功の可能性は上がります
銀行融資による資金調達は、知って・準備して・改善していくことで成功率を大きく高められます。今回ご紹介した、事業計画書の作成・決算書の改善・担保や保証人の準備・税金/社会保険料の納付・銀行との関係構築・自己資金の確保、それぞれにきちんと取り組むことがポイントです。
事業再生資金を銀行融資で……とお考えの経営者様は、ぜひ事業再生コンサルタントにご相談ください。
関連記事
-

-
 2025年09月24日資金繰りが厳しい…手遅れになる前の選択肢とは?赤字からの再生戦略と資金調達
2025年09月24日資金繰りが厳しい…手遅れになる前の選択肢とは?赤字からの再生戦略と資金調達資金繰りが厳しい…このままでは手遅れかもしれない。そんな不安を抱える経営者の方へ。赤字が出ていても、...
-

-

-