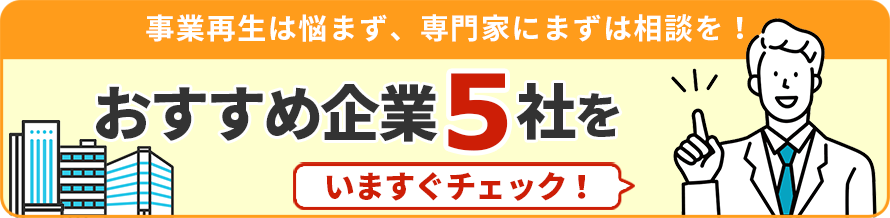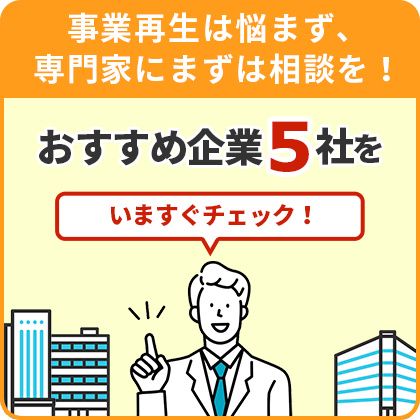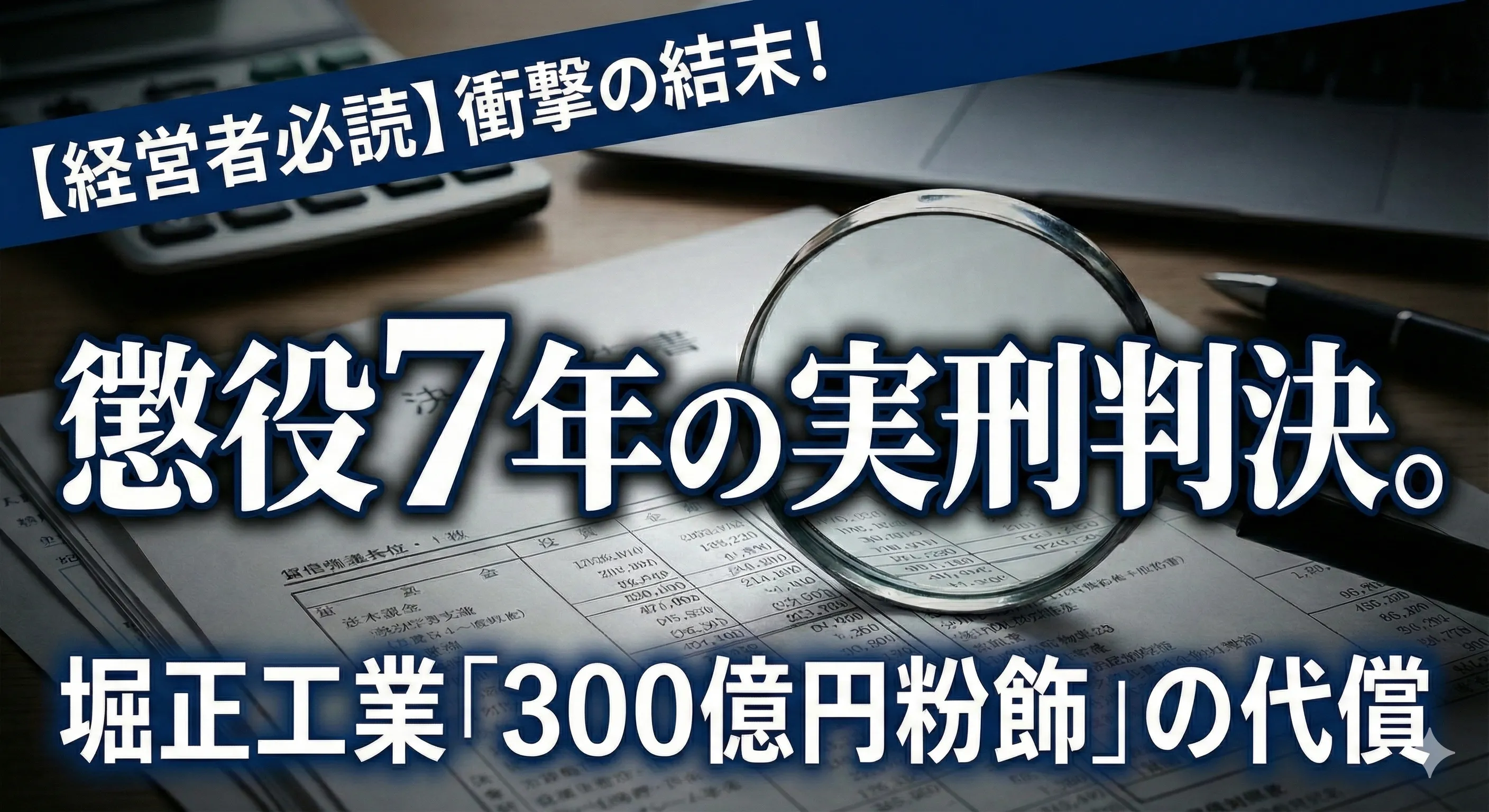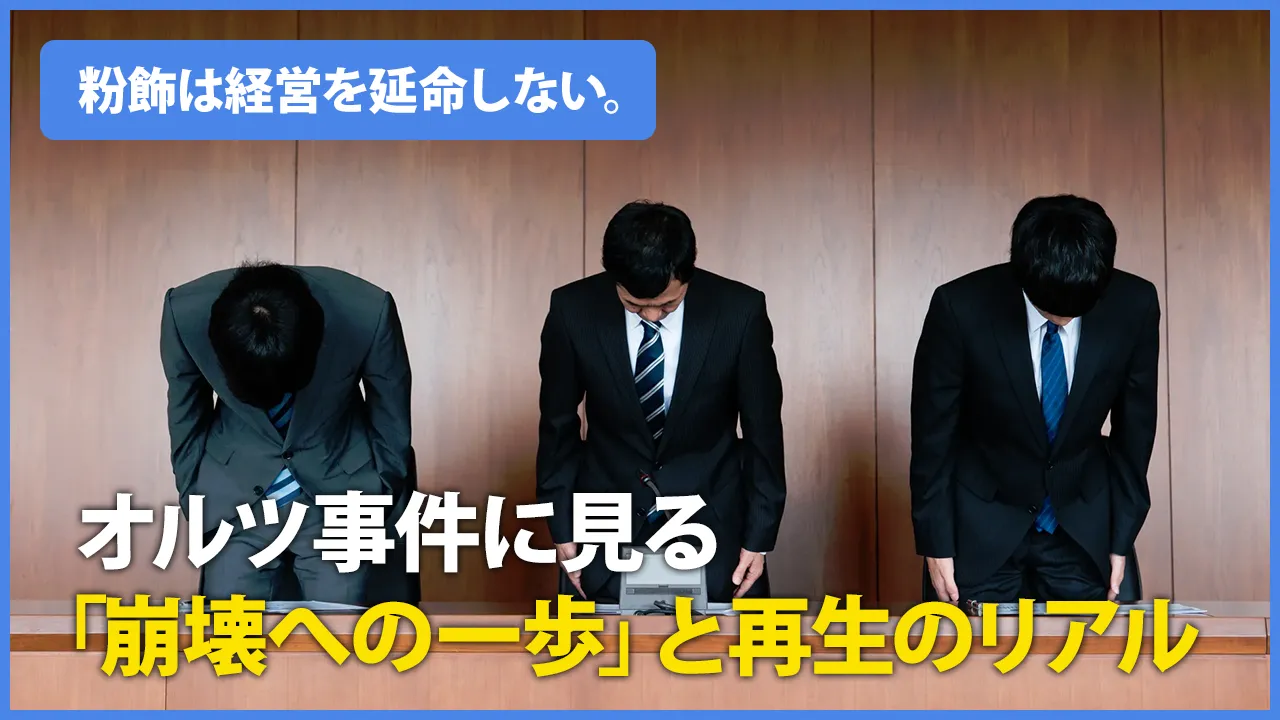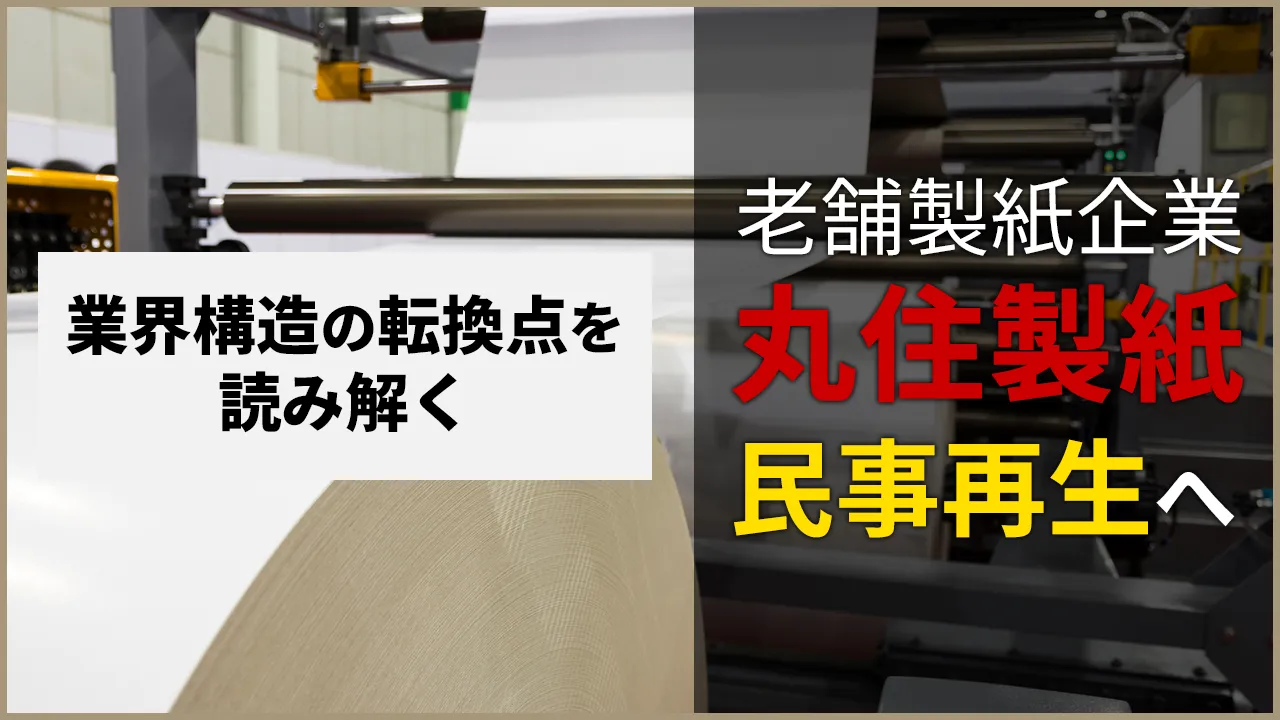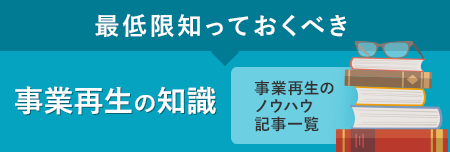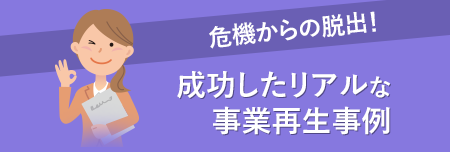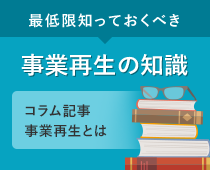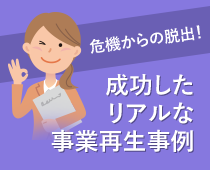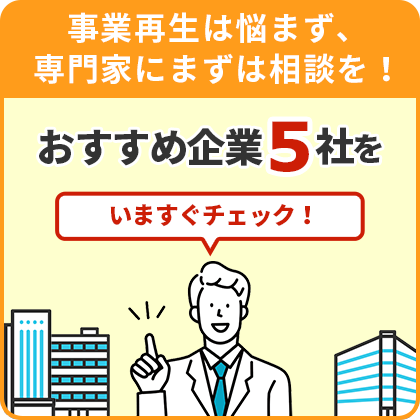かつて日産自動車の子会社である自動車部品大手メーカーとして、グループ全体で1兆円以上もの売上高を誇り、2024年には東京証券取引所への上場を目指していたカルソニックカンセイ(現マレリ)。
2022年には経営破綻し事業再生ADRを申請。米投資ファンドKKRに買収されたことで再スタートを切っていましたが、再度経営破綻し日本の民事再生法に相当する米連邦破産法 第11章(チャプター11)の申請手続きを2025年6月に開始しました。
短期間に、2度の経営破綻を引き起こしたマレリですが、今後どのように再建していくのでしょうか。
1度目の経営破綻の経緯はこちらの記事も参考にしてください。
日産旧子会社「マレリ」が負債1兆円超 事業再生ADRで4500億円の債権放棄
目次
この記事のポイント
この記事では、2度の経営破綻を引き起こしたマレリがこれからどのように再建していくのかを企業再生のプロが解説しています。マレリが2度も破綻した3つの理由に加え、経営再建に必要な出口設計とガバナンス戦略の重要性、「延命型再生」の限界などをまとめ、破綻は終わりではなく持続可能な再建は設計次第で実現できることをまとめました。破綻からの再建を目指している方にとっては必読の内容です。
破綻と再建の全体構造:民事再生からチャプター11へ
| 比較項目 | 1回目 | 2回目 |
|---|---|---|
| 破綻時期 | 2022年8月 | 2025年6月 |
| 手続きの国 | 日本(東京地裁) | アメリカ(デラウェア州) |
| 制度 | 民事再生法(簡易再生) | 連邦破産法 第11章 (チャプター11) |
| 原因 | ・コロナによる部品需要の急減 ・半導体不足 |
・日産・ステランティスの業績不振 ・再建後の借金 |
| 借金額 | 約1兆2000億円 | 約7113億円 |
| 債権者 | 日本の銀行・ファンド中心 | 外国のファンドや債券投資家中心 |
| 手続きの目的 | 会社を存続しつつ借金を整理し、もう一度立て直す | |
| 支援内容 | 銀行などから4500億円の債務放棄 | 約11億ドル(約1700億円)の資金を新たに調達 |
| 結果・影響 | 再建したが業績回復せず | 会社は存続、経営権は債権者側に移る見通し |
| 社員・工場などの影響 | 大きなリストラなし | 工場、雇用は基本維持される見込み |
マレリは、2022年8月に民事再生法が適用された後、2025年6月にはチャプター11と呼ばれているアメリカの連邦破産法 第11章を適用申請をするなど、2度も経営破綻を引き起こしています。会社を存続しつつ借金を整理し、再度企業を立て直していくために申請された再建型倒産手続きが行われた経緯を見ていきましょう。
1度目の再建:民事再生による「延命」スキームの実態
マレリは2022年、日本の民事再生法に基づく簡易再生手続きを用いて、債務の大幅圧縮と再建資金の確保に一度は成功していました。
当時の支援は国内のメガバンクを中心とするものであり、交渉環境も比較的整っていましたが、ただしこの再建はあくまで財務面の整理にとどまり、事業構造や競争力の本質的な改革は先送りされたままでした。
また、マレリの主力得意先である日産自動車や、イタリアとアメリカの自動車メーカーが対等合併したことで誕生した多国籍自動車メーカー「ステランティス」の業績が低迷していたことで資金計画に狂いが生じ、2024年12月からスタートする予定としていた金融機関への返済を延期する事態となっていました。
2度目の再建:海外ファンドが主導する“再再建”
マレリが民事再生法を適用された後は新たな資金繰り計画を策定し金融機関との調整をしていましたが、債権者間での合意が得られませんでした。そこで2025年6月11日には、米連邦倒産法第11章に基づく再建型倒産手続きである「チャプター11」の適用を申請。マレリは2度目の再建を目指すこととなったのです。
この2度目の再建の背景には、日本の金融機関が徐々に債権を手放した代わりに海外の投資ファンド(アメリカの投資ファンドであるSVPやフォートレス・インベストメント・グループなど)が大口債権者として登場していったことによる債権者構成の変化が大きく影響しています。
そこで新たな再建スキームは、実質的にこれらの海外投資ファンドによって設計されることになりました。
マレリが2度も破綻した3つの理由
 マレリほどの大企業が1度ならず2度も破綻した理由には、大きく分けて以下のような3つの原因がありました。
マレリほどの大企業が1度ならず2度も破綻した理由には、大きく分けて以下のような3つの原因がありました。
- ①抜本的な事業構造の改革ができなかったこと
- ②市場環境が悪化していたこと
- ③過去の買収の負担となっていたこと
①抜本的な事業構造の改革ができなかった
2022年にマレリが申請した民事再生ADRでは金融機関の一部が債権を譲渡しているほか、約4,500億円の債務免除と支援金を得ることができました。しかし、収益性の低い部門の整理や製品ラインの再構築、海外・新興国市場への戦略転換といった抜本的な改革は先送りとなっていたのです。
これらのことによって結果的に短期的な延命策にとどまり、根本的な収益改善には至りませんでした。
②市場環境の悪化
自動車業界はここ数年で、EV化とソフトウェア中心の車両開発が急速に進展していました。
ただマレリでは売上の多くを日産自動車に依存していました。そのためマレリには、エンジンやモーターなどの動力源から発生した力を自動車の駆動輪に伝える装置であるパワートレインや排気系など、内燃機関中心となる従来からのガソリン車における技術ポートフォリオが多く、EV分野への転換が遅れていたのです。
これはマレリのルーツが、ラジエーターの生産を手がけていた日本ラヂヱーター製造だったことにも起因しています。
また、中国系や韓国系の部品メーカーとの価格競争にも苦戦していたほか、大手顧客である日産自動車を中心とした完成車メーカーも生産台数を抑制していました。特に日産自動車の世界販売台数は2017年度の577万台をピークに、2024年度には334万台と大幅に落ち込んでいました。
これらの事実により、マレリへの受注も伸び悩んでいたのです。
③過去の買収の負担
マレリは日産自動車の自動車部品メーカーの子会社であった「カルソニックカンセイ」から、2017年には米投資ファンドであるKKRの子会社となっています。そしてその後の2019年には、同社の支援でイタリアの自動車メーカーFCA(フィアット・クライスラー・オートモービルズの略称)の自動車部品部門「マニエッティ・マレリ」を約7200億円で買収しています。
このような大型買収をした結果、長年にわたって以下の要因がマレリの経営を圧迫していたのです。
- ●組織・文化の統合失敗
- ●重い借入金と償却負担
- ●投資回収の遅れ
経営再建に必要な出口設計とガバナンス戦略
 企業が財務再建した後に、再建後の企業は誰が支配し、何をもって成功とするかといった出口設計が曖昧なままでいると、一度破綻し再建した企業でも再々度破綻をする可能性があります。そうならないためには、以下のような出口戦略を策定しておくことが不可欠です。
企業が財務再建した後に、再建後の企業は誰が支配し、何をもって成功とするかといった出口設計が曖昧なままでいると、一度破綻し再建した企業でも再々度破綻をする可能性があります。そうならないためには、以下のような出口戦略を策定しておくことが不可欠です。
- ●外部資本とのガバナンス設計
- ●経営権の維持
- ●再成長戦略の構築
マレリに学ぶ「延命型再生」の限界とは?
 マレリが取っていたような、会社を生き延びさせるだけの延命型の再生方法では限界があります。破綻企業が再度再生していくためには、以下の内容を参考に持続可能な再生方法を採用していくようにしましょう。
マレリが取っていたような、会社を生き延びさせるだけの延命型の再生方法では限界があります。破綻企業が再度再生していくためには、以下の内容を参考に持続可能な再生方法を採用していくようにしましょう。
- 企業再建は「債務減免」方式だけでは成功しません。
- 「再建スキーム」「資本構成」「再成長戦略」が一体でなければ再々破綻は避けられません。
- 再建企業には、再建後の事業戦略を含めたトータルな設計力が求められます。
マレリ再建に関するQ&A
ここまで記事をお読みいただき、「マレリでは、これってどうなの?」という疑問が浮かんできたという方もいらっしゃるかもしれません。
ここからは、事業再生のプロがマレリの再建に関する、みなさんが抱きがちな疑問点にQ&A形式でお答えします。ぜひ最後まで目を通して疑問点をクリアにしてみてください。
Qなぜ日本の民事再生ではなく、アメリカのチャプター11を使ったのか?
A2025年時点におけるマレリの債権者の大多数は海外ファンドであったため。再建の主導権は外資側に移っていました。そこで、民事再生法よりも柔軟でスピーディーなスキームを持つアメリカのチャプター11が選ばれたのです。
チャプター11には、事業を継続しながら債務の削減や再編ができ、企業が清算されずに再建を目指せるという大きなメリットを持っていました。
また、日本の民事再生よりもアメリカのチャプター11の方が債権回収や経営関与がしやすいというファンド側にとってのメリットもありました。
QサプライヤーやOWMメーカーへの影響はある?
A現時点では、主要取引先への供給は維持されており、部品の生産・販売などの企業活動・運営には影響は及ばないものと見込んでいます。マレリでも「今後も、顧客、サプライヤー、パートナーと緊密に協力し、将来の自動車の発展に向け、モビリティを変革する先進技術のポートフォリオの革新と投資に取り組んで参ります」と発表しており、影響はないと考えています。
ただし、与信管理や契約条件の見直しは進行中であり、業界全体でリスク分散の動きが強まっていることには注意してください。
Q2度目の再建が上手くいく可能性はある?
Aマレリでは現在、法的整理手続き中の企業に対して事業継続に必要な資金を融資するDIPファイナンスを11億ドル(日本円で1,600億円以上)も確保しているほか、事業の選択と集中も進んでいるため、企業再建していくチャンスは十分あります。
ただしそこに本質的な改革が伴わなければ、再建がただの延命に終わるリスクも持っており、経営主導権を誰が握るかが2度目の再建の成否を分けるでしょう。
破綻は終わりではない――持続可能な再建は設計次第で実現できる
 経営破綻の企業を再生していくときに、財務リストラだけを実行するのでは不十分であり、結局は「延命型再生」に終わってしまう可能性があります。そこで再構築する際に、「制度」「資本」「ガバナンス」を一体で再設計していくことが大切です。その際に主体的な意思決定と出口設計があれば、破綻は再構築の機会にも変えてくれます。
経営破綻の企業を再生していくときに、財務リストラだけを実行するのでは不十分であり、結局は「延命型再生」に終わってしまう可能性があります。そこで再構築する際に、「制度」「資本」「ガバナンス」を一体で再設計していくことが大切です。その際に主体的な意思決定と出口設計があれば、破綻は再構築の機会にも変えてくれます。
マレリの失敗と教訓は、今後の企業再建戦略を考える上で貴重な実例となるでしょう。
関連記事
-
 2025年12月22日堀正工業はなぜ一線を越えたのか? 300億円粉飾事件の全貌と「嘘」の代償
2025年12月22日堀正工業はなぜ一線を越えたのか? 300億円粉飾事件の全貌と「嘘」の代償2023年に発覚した堀正工業の粉飾倒産事件。「老舗の中堅商社が倒れた」という衝撃が走り、金融機関を巻...
-
 2025年10月27日【実例から学ぶ】「AIサービス」オルツの110億円粉飾と経営陣逮捕の背景
2025年10月27日【実例から学ぶ】「AIサービス」オルツの110億円粉飾と経営陣逮捕の背景経済界を揺るがしたオルツ粉飾決算事件のような破産劇は、決して一部の特殊な企業だけの話ではありません。...
-
 2025年05月29日【2025年最新版】旧ビッグモーターが会社分割方式でWECARSを設立!再生状況の動向を解説
2025年05月29日【2025年最新版】旧ビッグモーターが会社分割方式でWECARSを設立!再生状況の動向を解説「店頭の街路樹に除草剤を散布する」といった報道などで大きな騒動を呼んでいたビッグモーター。2023年...
-

-