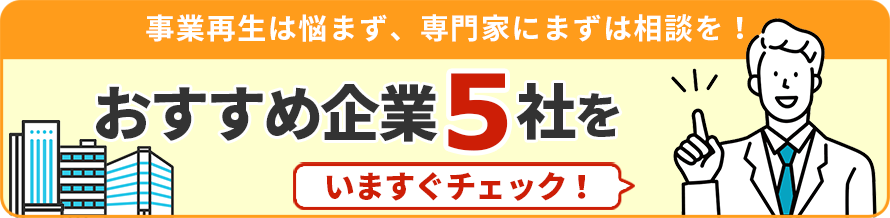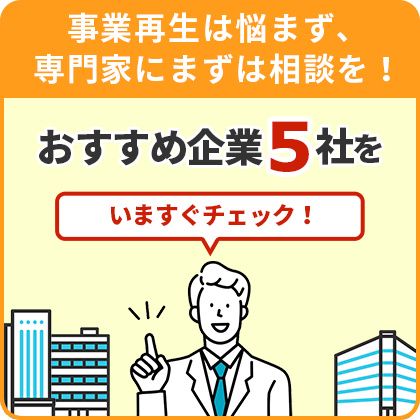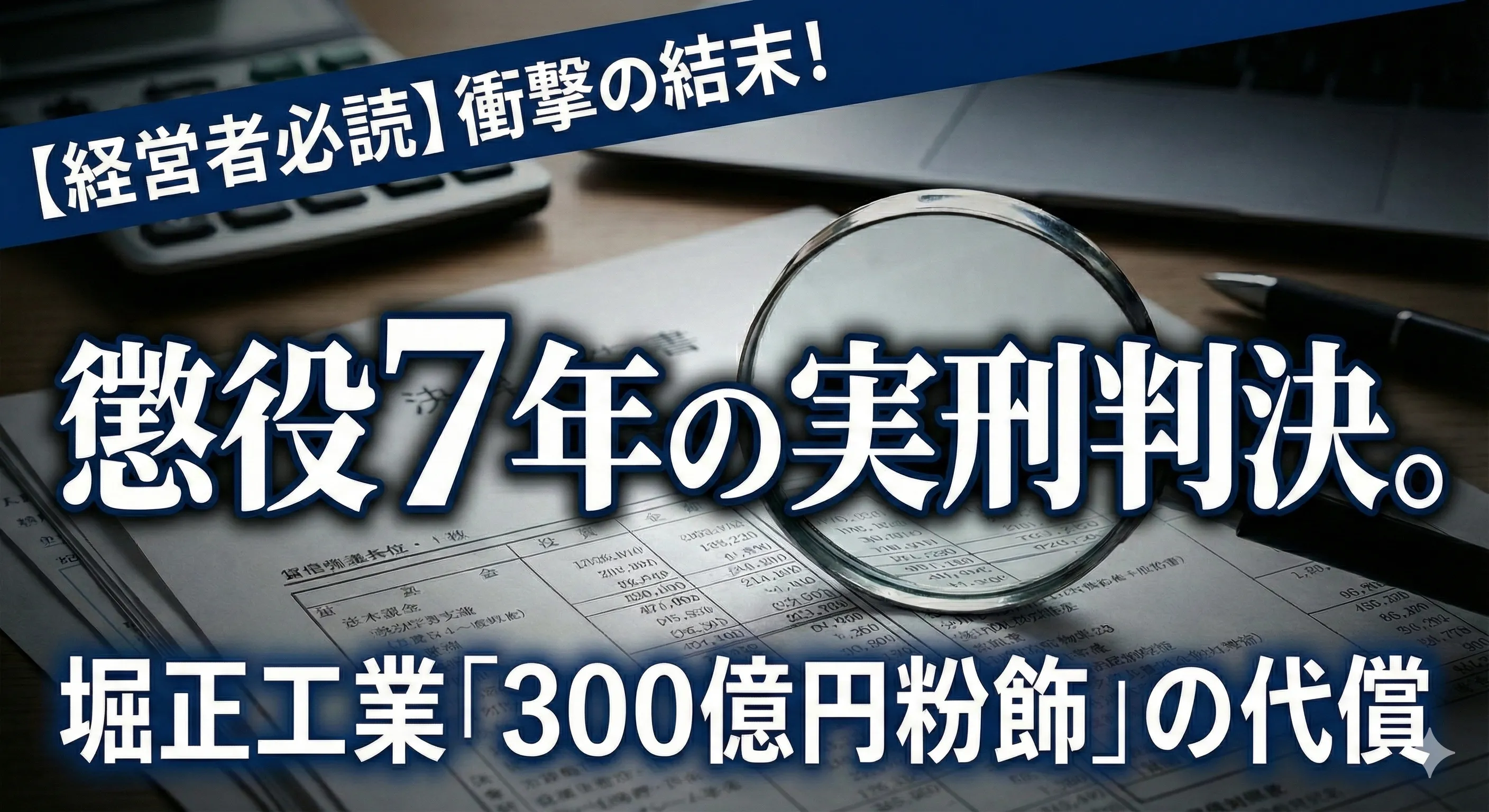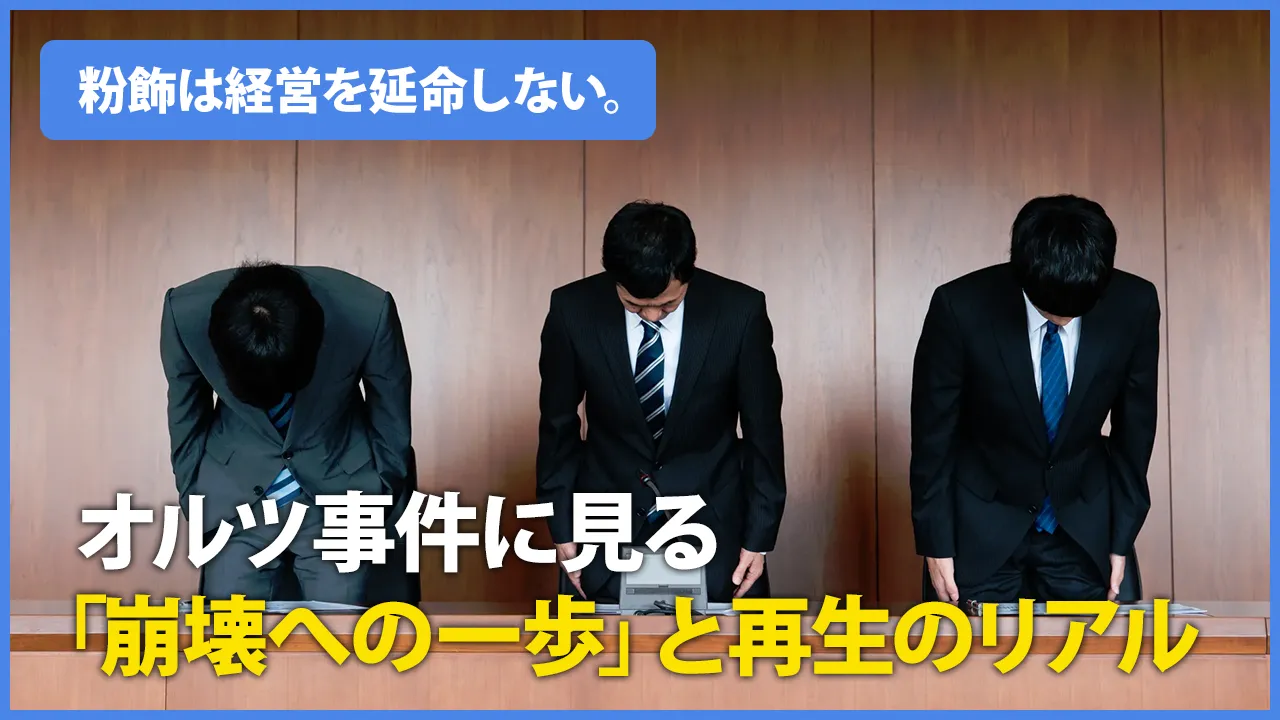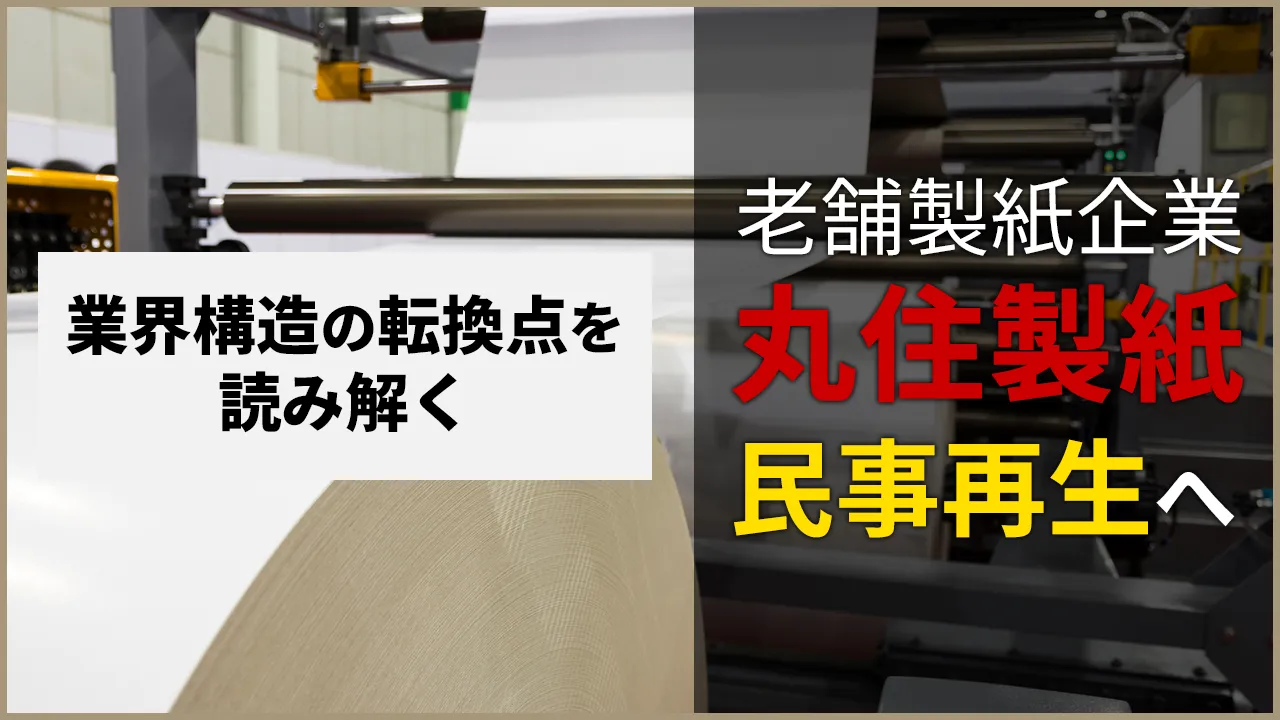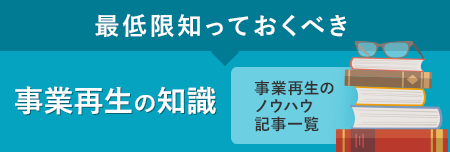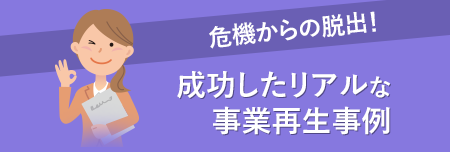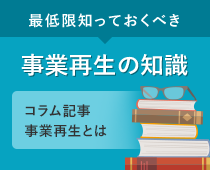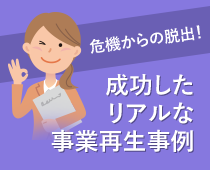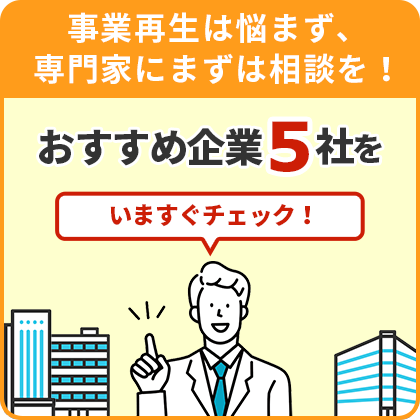鹿児島県鹿児島市に本社を置き、鹿児島と宮崎で5店舗を展開する伝統的な百貨店「山形屋」は、百貨店に対するさまざまな影響を受け近年では経営悪化が続いていました。そして2023年12月には事業再生ADRを申請。2024年5月にはそれが承認されています。
本記事では、どのような状況で事業再生ADRを申請するべきなのかについて、具体的な事例を紹介します。
目次
山形屋とはどんな企業?
 山形の経済を支えていた紅花仲買と呉服太物行商を興し、大阪・京都へ立ち回り、八面六臂の大活躍をしていた山形屋の始祖・初代源衛門。薩摩藩の商人招致を知り、鹿児島城下木屋町(のちの金生町)に呉服太物店を構え、山形屋と称して1751年(宝暦元年)に呉服店として創業した老舗の百貨店です。明治時代中頃には百貨店へと業態を変え、大正時代初期には既に近代的なデパート建築を行っています。
山形の経済を支えていた紅花仲買と呉服太物行商を興し、大阪・京都へ立ち回り、八面六臂の大活躍をしていた山形屋の始祖・初代源衛門。薩摩藩の商人招致を知り、鹿児島城下木屋町(のちの金生町)に呉服太物店を構え、山形屋と称して1751年(宝暦元年)に呉服店として創業した老舗の百貨店です。明治時代中頃には百貨店へと業態を変え、大正時代初期には既に近代的なデパート建築を行っています。
本店は鹿児島県鹿児島市に位置しており、「信用第一」「顧客本位」「あくまでも堅実に」を社是とする地域密着型のデパートとして南九州地域では長らく愛されてきました。
山形屋の概要と沿革
 1917年(大正6年)にルネッサンス式鉄骨鉄筋コンクリート造り、地下1階~地上4階の新店舗を落成させた山形屋は、1937年には「株式会社山形屋」と改称。個人経営から資本金100万円の「株式会社山形屋呉服店」として生まれ変わりました。
1917年(大正6年)にルネッサンス式鉄骨鉄筋コンクリート造り、地下1階~地上4階の新店舗を落成させた山形屋は、1937年には「株式会社山形屋」と改称。個人経営から資本金100万円の「株式会社山形屋呉服店」として生まれ変わりました。
戦後は、東京、大阪、京都、名古屋各地の主力取引先110数社で「山形屋会」連合会を結成し、1963年に新旧両本館4,951㎡の増築と内部、外装とも一新し、本店新装工事を完成させるなど、発展を続けてきました。その後も山形屋は21世紀に通用する都市型百貨店を目指し、1998年にはドーム屋根の塔屋が印象的な大正6年当時のルネッサンス調外壁が復元されています。その夜間のライトアップは通行客を魅了し、鹿児島に明るい話題を提供してきました。
会社概要
| 会社名 | 株式会社山形屋 |
|---|---|
| 創業 | 宝暦元年(1751年) |
| 設立 | 大正6年(1917年) |
| 代表者 | 代表取締役社長 岩元修士 |
| 事業内容 | 百貨店 |
| 資本金 | 1億円 |
| 売上高 | 367億円 |
| 従業員数 | 733人(令和5年4月1日現在) |
| 営業所 | 外商出張所 |
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市金生町3番1号 代表 (099)227-6111 |
| 営業時間 | 10:00~19:00 |
引用元:会社案内 | 企業情報 | 山形屋 (やまかたや) グループ百貨店
経営理念
| ①社是 | 信用第一 顧客本位 あくまでも堅実に |
|---|---|
| ②基本方針 | 山形屋の原点は 「お客様の喜びは自分の喜びとする心」 である。 山形屋の目標は 「地域の人々に愛される日本一の百貨店」である。 山形屋の使命は 「良い街の良い百貨店の実現」 である。 |
| ③スローガン | The Good & New Department Store YAMAKATAYA ザ グッド アンド ニュー デパートメント ストア ヤマカタヤ |
引用元:会社案内 | 企業情報 | 山形屋 (やまかたや) グループ百貨店
会社沿革
| 1751年(宝暦元年) | 源衛門、紅花仲買と呉服太物行商を興し大阪・京都へ立ち回る。 |
|---|---|
| 1772年(安永元年) | 薩摩藩の商人招致を知り、鹿児島城下木屋町(のちの金生町)に呉服太物店を構え、山形屋と称する。 |
| 1888年(明治21年) | このころ、山形屋 岩元信兵衛本店、同大阪支店と呼ぶようになる。 |
| 1916年(大正5年) | ルネッサンス式鉄骨鉄筋コンクリート(地下1階~地上4階)の新店舗落成。 |
| 1917年(大正6年) | 個人経営から資本金100万円の「株式会社山形屋呉服店」を設立。 後(1937年)に「株式会社山形屋」と改称する。 |
| 1925年(大正14年) | 友の会「七草会」を創始する。 |
| 1926年(大正15年) | 優良児審査会(現:南日本赤ちゃん健康相談会)を創始する。 |
| 1932年(昭和7年) | 新館(地下1階~地上7階、売場面積延べ10,403㎡)落成。 |
| 1945年(昭和20年) | 本社、空襲により被災。 |
| 1953年(昭和28年) | 東京、大阪、京都、名古屋各地の主力取引先110数社で、「山形屋会」連合会を結成。 |
| 1957年(昭和32年) | 1階~4階 エスカレーター運転開始。 |
| 1963年(昭和38年) | 新旧両本館4,951㎡の増築と内部、外装とも一新、新装工事完成。売場面積16,229㎡となる。(右写真) |
| 1972年(昭和47年) | 全館増築完成・新装オープン。(売場面積22,816㎡となる) |
| 1974年(昭和49年) | 山形屋商品試験室、開設。 |
| 1983年(昭和58年) | 1号館電車通り側、シースルーエレベーター完成。 |
| 1984年(昭和59年) | 山形屋2号館完成オープン。当日の入店者15万人を記録。 |
| 1986年(昭和61年) | 山形屋オリジナルブランド「ナガサワワイン」を日本国内総販売元として販売開始。 |
| 1988年(昭和63年) | 山形屋厚生基金郡山福祉センターが、日置郡郡山町に新装落成。 |
| 1990年(平成3年) | 山形屋サテライトショップ谷山オープン。 |
| 1992年(平成5年) | 山形屋システム開発部を独立させ、新会社「株式会社山形屋情報システム」が発足。 |
| 1995年(平成7年) | 山形屋サテライトショップ姶良オープン。 |
| 1998年(平成10年) | 山形屋1号館外壁工事竣工。ルネッサンス調のデザインに一新。 |
| 2005年(平成17年) | 鹿児島本港区のドルフィンポートに薩摩酒蔵、故郷市場、ミディソレイユ、ポルトカーサなど出店。(賃貸借契約満了に伴い、2020年(令和2年)3月閉鎖) |
| 2015年(平成27年) | 1号館7階フロアに山形屋食堂、ビストロ ル ドーム(現在 レストラン ル ドーム)、ななテラスがオープン |
引用元:会社沿革 | 企業情報 | 山形屋 (やまかたや) グループ百貨店
山形屋が事業再生ADRをすることになるまでの経緯
 「ふるさとのデパート」というキャッチコピーで長年にわたり地域に親しまれ、デパートとして順調に成長しているかに見えていた山形屋。ですが2020年から発生したコロナ禍の状況においては、店舗の長期休業や営業時間の短縮、催事の中止などを余儀なくされました。この予期しない出来事により、来店客数や売上高が大幅に減少し赤字額が膨らんだことで事業再生ADRの申請を余儀なくされたのです。
「ふるさとのデパート」というキャッチコピーで長年にわたり地域に親しまれ、デパートとして順調に成長しているかに見えていた山形屋。ですが2020年から発生したコロナ禍の状況においては、店舗の長期休業や営業時間の短縮、催事の中止などを余儀なくされました。この予期しない出来事により、来店客数や売上高が大幅に減少し赤字額が膨らんだことで事業再生ADRの申請を余儀なくされたのです。
事業再生ADRのメリット・デメリットや手続の流れの詳細については以下のページをご覧ください。
事業再生ADRとは? メリット・デメリット、手続の流れをわかりやすく解説
経営悪化の6つの理由
山形屋が事業再生ADRを申請することになった背景には、以下のような6つの経営不振となった要因があります。
- ①経営環境の厳しい状況
- ②消費者行動の変化
- ③競争激化
- ④経営体力の低下
- ⑤コロナ禍の影響
- ⑥利益率の低下
これら6つの要因が重なってしまったことで最終的に6期連続の最終赤字を計上。結果的に経営不振に陥いるようになりました。以下で、6つの要因の内容について解説していきます。
①経営環境の厳しい状況
山形屋では、経営状況が悪化するような以下5つの環境が重なってしまいました。
- 1.人口減少
- 2.長引くデフレ
- 3.郊外への大型商業施設の進出
- 4.インターネット通販の台頭
- 5.新型コロナウイルス禍の影響
とくにインターネット通販の台頭は大きいものがありました。店舗でサイズや色合いを確認し「購入はもっとも安いネット通販で購入する」という消費者が増え、衣料品や化粧品、県外の特産品などの同じ商品ならデパートよりもインターネット通販で購入することが増え、デパートにおける消費者の買い回りが減少する要因となっていきました。
②消費者行動の変化
消費者行動の変化も大きな要因のひとつです。デパートの主要購買層は団塊世代層になりますが、2010年前後から一斉に退職時期を迎えたことで消費減少を招いたのです。
また、団塊世代よりも若年の層についても、消費者行動の変化は①で言及したようにインターネット通販の普及による店舗での買い回り減少といった結果で表れてきました。そのほかファミリー層についても、ただ単に買物を楽しむだけでなく飲食や買物などを「時間間消費型」で楽しめる大型商業施設が多数オープンしたことも消費者が流出した原因となります。
③競争激化
鹿児島中央駅や鹿児島市南部エリアには、2004年に「アミュプラザ鹿児島」、2007年に「イオンモール鹿児島」といったシネマコンプレックス(複合型映画館)が併設し、商品を購入しなくても料金をかけずに飲食や買物などを長時間できる大型商業施設が相次いで開店していきました。鹿児島中央駅東口から約10分、鹿児島駅から約5分という場所に位置する山形屋の本店は、このような大型商業施設との競合にもろにされされるようになったのです。
④経営体力の低下
山形屋が、都市間競争や郊外大型商業施設への対抗策として。さらにそれに加えて、2011年の九州新幹線全線開業を見据え現在3号館を新規2号館として建て替え、総売り場面積を1.5倍に増床する計画を打ち出したのは2007年8月ことです。しかしそのときはリーマンショックの影響を受けたことで計画凍結を2009年に発表したのでした。
その当時から山形屋における経営体力の低下が始まっており、2007年から15期連続で減収が続いていました。売上高のピークだった1997年の年間売上高約680億円から2021年には年間売上高約312億円まで右肩下がりで減少しており、事業再生ADRを申請する前の2023年には既に、グループ会社を含めて360億円の負債を抱えていました。
⑤コロナ禍の影響
山形屋の経営悪化にもっとも大きな影響を与えたのは、2020年から始まった新型コロナウイルスの感染拡大かもしれません。2020年には山形屋の店舗が約3週間の休業や営業時間の短縮をせざるを得なくなり、消費者が密集して集まる催事は中止を余儀なくされています。
また当時は外出自粛要請も長引いた結果、2020年度における来店客数は前期比35.1%減少を招いています。その結果、売上高は25.9%も減り、経常損益は14億1529万円の赤字を記録するまでとなりました。
⑥利益率の低下
山形屋では減少を続ける収益に対し、経費節減などで対応してきました。販売管理費は2014年2月期から2023年同期における9年間で30%近くを削減しており、社員数も2014年2月期から2022年同期までに530人以上減らしています。
しかし社員数を削減した分、自主販売も減り、その逆にインショップ(委託販売)が増えて納入掛け率や返品経費などが上昇。その分、2014年から2022年にかけての粗利益率が2.78ポイントも低下し、利益率の悪化を招くことになりました。
その結果、6期連続の最終赤字を記録しています。
近年の事業再生の取り組み
このように経営状況の悪化が続いていた山形屋では、2023年12月28日に事業再生ADRを申請し鹿児島銀行の支援を受け経営再建に乗り出すこととなりました。そして2024年5月28日には、鹿児島銀行を含む17金融機関全会一致で合意しています。
その後、債権者会議を4回開催することで、そこにおいて事業再生計画案の概要説明や内容を協議してきました。最終的な会議において、鹿児島銀行を含んだ全17の金融機関が合意して事業再生計画が成立。その結果、山形屋の営業は続けるとしています。
山形屋の再生計画とこれから
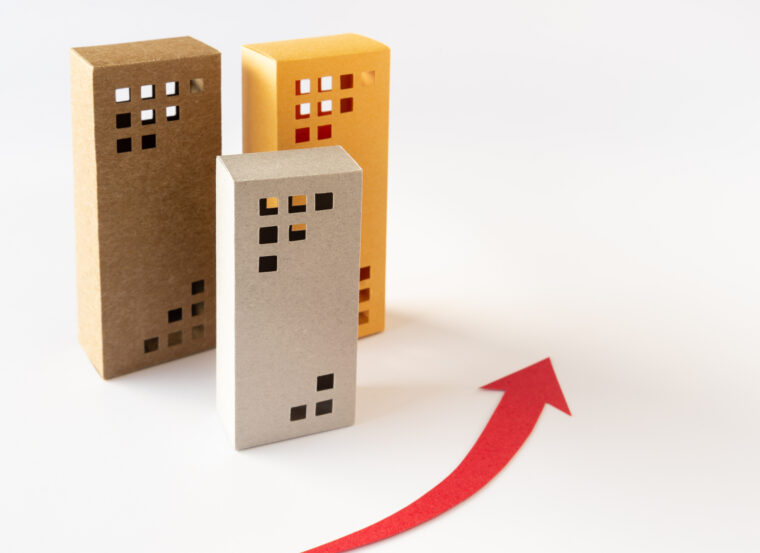 2024年5月28日に、全17の金融機関が事業再生計画案に合意し成立した山形屋の事業再生ADR。今後5年間は合意した計画に沿って経営再建を進めるとしています。
2024年5月28日に、全17の金融機関が事業再生計画案に合意し成立した山形屋の事業再生ADR。今後5年間は合意した計画に沿って経営再建を進めるとしています。
この事業再生計画では、組織・人員体制のスリム化や不動産売却などを柱にしながら、事業見直しと財務健全化を目指していくとしています。しかし従業員の解雇や主体的な退職をつのる希望退職は実施せず、人件費の削減は正社員の自然減とアルバイトの低減で行っていく予定です。また、グループ会社の川内山形屋、国分山形屋、宮崎山形屋、日南山形屋などの各店舗では組織統合を行うものの閉店はしないほか、宮崎、霧島、薩摩川内、日南で展開する山形屋各店舗の閉鎖は予定していないため、山形屋は約360億円の負債を抱えながらも経営再建を進めていくことが可能となりました。
組織再編
山形屋が事業再生をしていくにあたって組織再編が行われていますが、その内容は以下となります。
- ・代表取締役には山形屋の代表取締役会長・岩元純吉氏が就任
- ・2024年6月24日付けで山形屋ホールディングスを設立
- ・現在24社あるグループ関連会社を15社へと再編
役員としてメインバンクにある鹿児島銀行から2名、東京の投資ファンドから1名を受け入れるなど、外部人材を受け入れることで財務の透明性を確保して、経営監視体制を強化します。
店舗活性化
山形屋では店舗を活性化していくために、今後は以下のような施策を実行していきます。
・新規テナントの導入
店舗活性化の第1弾としてフロアを一部改装し、丸善ジュンク堂書店の文具専門店である「丸善」と家電量販店の「エディオン」をテナントとして山形屋内に出店します。
・アプリの導入
専用の山形屋公式スマホアプリを立ち上げて、来店時のポイント付与で顧客の増加を図っていくだけでなく、イベントや洋服のオーダーメードなどで顧客の動きを事前に把握し業務の効率化を進めていきます。デジタル活用に踏み込んでいくことで、新規顧客の獲得やリピーター促進を目指していきます。
山形屋によると、リニューアルした店舗には訪れる顧客が順調に増え、スマホアプリの利用者も伸びています。今後のテナント見直しや改装なども現在、計画に基づいて準備を進めており、正式に決まり次第、順次公表していくということです。
業務改革
山形屋では、グループ24社を束ねる、純粋持ち株会社山形屋ホールディングスを設立。鹿児島銀行、ルネッサンスキャピタルから役員が入り、ガバナンスを強化するという。山形屋ホールディングス設立後には、国分山形屋、川内山形屋、山形屋パーキング、サービス業のワイズ、小売業のトウェンティ・ワン、不動産業・保険代理業の金生産業という6社を山形屋に、日南山形屋と宮坂山形屋食堂を宮崎山形屋に、卸売業の山形屋産業開発を山形屋商事に、それぞれ合併しています。
また、利益率の悪化を招く結果となっていた店舗人員削減は止め、逆に店舗人員を強化するなど適正な人員配置に取り組んでいます。組織・人員体制としては正社員数の自然増減で調整し、今後も大規模なリストラなどは行っていかないとしています。
財務健全化
山形屋は約360億円の負債を抱えていたため、この負債を軽減するための施策を講じています。その内容としては、借入金の一部を株式に転換するデット・エクイティ・スワップ(DES)で40億円を調達。借入金の一部を劣後ローンに交換するデット・デット・スワップ(DDS)で70億円を調達する計画としています。
山形屋では金融支援や遊休資産の売却に取り組むことによって、残り250億円の負債の返還については返済の5年間猶予を行い、2029年2月期にはグループ売上高720億円、営業利益16億円を目指すとしています。
今回の事例から学ぶこと
 長年にわたり地域に親しまれ、順調に成長してきていた老舗企業でも、経営環境の厳しい状況や消費者行動の変化、競争激化、経営体力の低下、コロナ禍の影響、利益率の低下などにより、山形屋のように経営悪化に陥ることもあります。
長年にわたり地域に親しまれ、順調に成長してきていた老舗企業でも、経営環境の厳しい状況や消費者行動の変化、競争激化、経営体力の低下、コロナ禍の影響、利益率の低下などにより、山形屋のように経営悪化に陥ることもあります。
その際には自力再生にこだわるのではなく、私的整理の1つである「事業再生ADR」を申請することで、廃業に終わらず企業を存続しながら経営再建していくことは可能です。
自社で悩んだときは、専門家に相談を
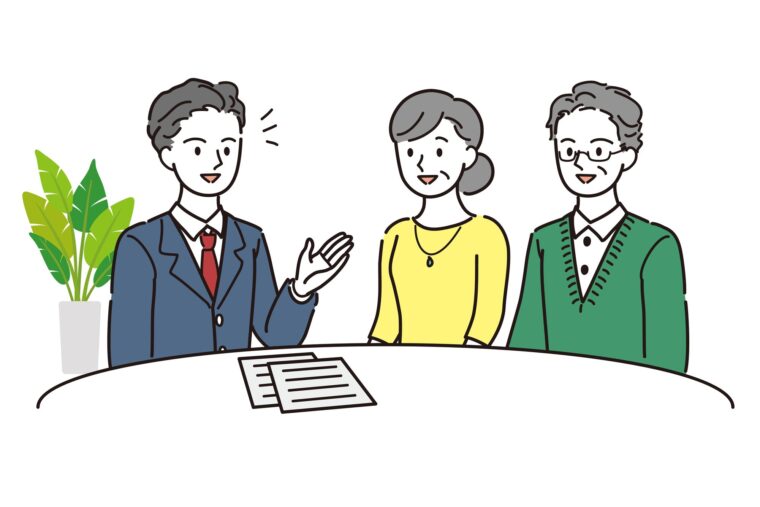 会社の経営が悪化して頭を抱えて苦しんでいる事業・雇用を守りたい中堅・中小企業の経営者の方は、1人で悩んでいても解決できません。会社を立て直すためには早めに専門家への相談をおすすめします。
会社の経営が悪化して頭を抱えて苦しんでいる事業・雇用を守りたい中堅・中小企業の経営者の方は、1人で悩んでいても解決できません。会社を立て直すためには早めに専門家への相談をおすすめします。
事業再生ADRを行うべきか、他の手法を採用すべきかという判断は難しいものがあります。そこでまずは事業再生の専門家に相談することで、自社に合った手法を検討してみるようにしましょう。
関連記事
-
 2025年12月22日堀正工業はなぜ一線を越えたのか? 300億円粉飾事件の全貌と「嘘」の代償
2025年12月22日堀正工業はなぜ一線を越えたのか? 300億円粉飾事件の全貌と「嘘」の代償2023年に発覚した堀正工業の粉飾倒産事件。「老舗の中堅商社が倒れた」という衝撃が走り、金融機関を巻...
-
 2025年10月27日【実例から学ぶ】「AIサービス」オルツの110億円粉飾と経営陣逮捕の背景
2025年10月27日【実例から学ぶ】「AIサービス」オルツの110億円粉飾と経営陣逮捕の背景経済界を揺るがしたオルツ粉飾決算事件のような破産劇は、決して一部の特殊な企業だけの話ではありません。...
-

-
 2025年05月29日【2025年最新版】旧ビッグモーターが会社分割方式でWECARSを設立!再生状況の動向を解説
2025年05月29日【2025年最新版】旧ビッグモーターが会社分割方式でWECARSを設立!再生状況の動向を解説「店頭の街路樹に除草剤を散布する」といった報道などで大きな騒動を呼んでいたビッグモーター。2023年...
-