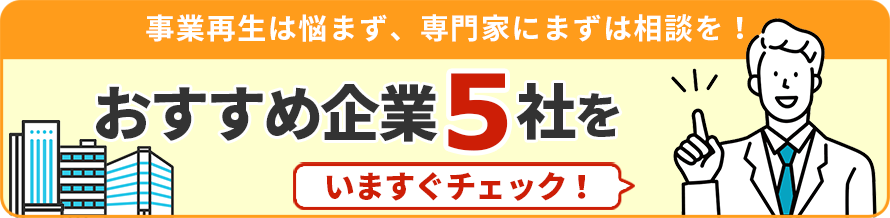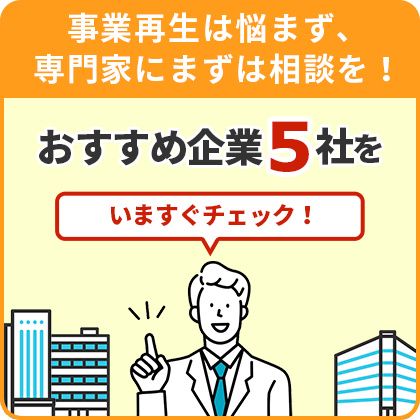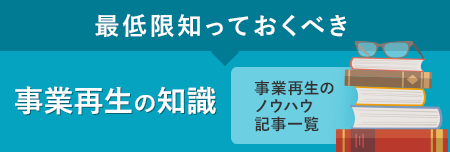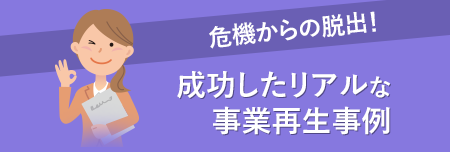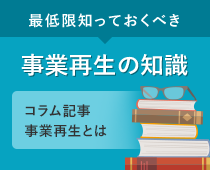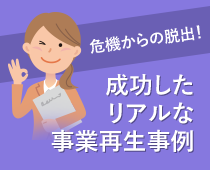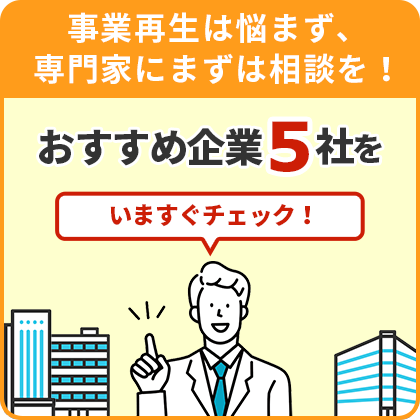2025年10月30日
目次
資金繰り悪化の元凶「二重の脅威」と、今こそ対策が必要な理由
現在、多くの中小企業が深刻な資金繰り危機に直面しています。その元凶は、「コロナ融資の返済本格化」と「歴史的な物価高騰」という、まさに「二重の脅威」です。
コロナ禍を支えたゼロゼロ融資の元本返済が始まりキャッシュフローを圧迫する一方で、原材料費やエネルギーコストの高騰が利益を削っています。多くの企業がコスト上昇分を価格に転嫁できず、売上はあっても手元資金が枯渇していくという厳しい状況です。
このままでは、黒字であっても倒産に至るケースや、廃業を選択せざるを得ない企業が急増しかねません。こうした危機的状況を乗り越え、事業の継続と立て直しを図る時間を確保するため、今まさに公的支援を活用した対策が急務となっています。
この喫緊の課題である資金繰り圧迫を直接的に緩和する、最も有効な手段の一つが「公的制度を活用した借換え」です。
公的制度を活用して借換えを行うメリット
公的な特例融資や信用保証制度を活用して既往債務の借換え(債務の一本化や返済条件の変更)を行う最大のメリットは、喫緊の課題である資金繰りを安定化させ、事業継続に必要な時間を確保することにあります。借換えによって、既存債務の返済条件(特に返済期間や据置期間)を大幅に延長し、月次のキャッシュアウトを劇的に抑制することが可能となります。
さらに重要な点は、これらの制度を活用することで、企業の長期的な「信用格付け」の防衛につながるという戦略的価値です。
資金繰りが悪化し、金融機関に個別に返済条件の変更(リスケジュール)を申し入れた場合、一般的に企業の信用格付けは低下する傾向にあります。しかし、本記事で紹介するような公的な特例制度や信用保証制度を利用して計画的に債務を再構築することは、自助努力と公的な裏付けがある再生プロセスへの参加と見なされます。
これにより、企業の金融機関からの評価や、将来的な取引先からの信認の維持に貢献し、長期的な企業価値の毀損を回避することができます。公的制度を活用した借換えは、短期的な延命措置であると同時に、将来的な追加融資や事業回復を見据えた「企業価値の防衛戦略」として機能します。
返済負担の軽減に活用できる主な公的制度(JFC・保証協会)
資金繰りに困る経営者が、既往債務の借換えや返済負担軽減のために利用できる公的な制度は、主に日本政策金融公庫(JFC)が提供するものと、信用保証協会が関与するものに大別されます。経営者はまず、自身の事業形態や既存債務の構成に基づき、最適な制度を選択する必要があります。
選択肢1:日本政策金融公庫(JFC)の特例制度
公庫融資借換特例制度について
社会的・経済的環境の変化や資金繰りの困難、経営改善の必要性などから、弁済(返済)に係る負担の軽減を必要としている方が利用できる制度です。既往の公庫融資の借換などを通じて、経営安定や中小企業者の自助努力による企業再建を支援することを目的としています。
| 公庫融資借換特例制度の概要 | |
|---|---|
| ご利用いただける方 | セーフティネット貸付制度(経営環境変化対応資金、金融環境変化対応資金)や、東日本大震災復興特別貸付、令和2年7月豪雨特別貸付、令和6年能登半島地震特別貸付、事業再生・企業再建支援資金、事業承継・集約・活性化支援資金、挑戦支援資本強化特別貸付、危機対応後経営安定貸付制度による貸付けを受ける方。原則として、既往の公庫融資の借換のほか、新規融資のご利用が必要です。 |
| 融資限度額 | 適用した特別貸付制度の貸付限度額 |
| 利率(年) |
適用した特別貸付制度に定める利率。 ただし、借換部分のうち、借換対象の貸付口の加重平均金利がご融資時の基準利率を上回る場合は、加重平均金利が適用されます。(挑戦支援資本強化特別貸付を除く) |
| ご返済期間 |
適用する制度により異なる。(例:経営環境変化対応資金・金融環境変化対応資金は8年以内、事業再生・企業再建支援資金は20年以内など) ※いずれも据置期間は原則1ヶ月以内 |
選択肢2:保証協会の特例制度
1.経営改善サポート保証(経営改善・再生支援強化型)制度について
物価高や人手不足等の影響により、厳しい経営状況にある中小企業者の早期の経営改善や事業再生を後押しするための保証制度です。
これは、2025年3月末で終了した「感染症対応型」の後継制度として創設されたもので、引き続き信用保証料の事業者負担を大幅に引き下げる措置(事業者負担 0.3%)が設けられています。認定経営革新等支援機関が策定を支援した事業再生計画などが対象となります。
| 経営改善サポート保証(経営改善・再生支援強化型)制度の概要 | |
|---|---|
| 保証限度額 | 2億8,000万円(一般の普通・無担保保証とは別枠) |
| 保証割合 | 責任共有保証(80%保証)。ただし100%保証およびコロナ禍のセーフティネット保証5号からの借換については100%保証。 (いずれも保証付きの既往借入金の範囲内の額を借り換える場合に限る。) |
| 保証料率 | 0.3% (国による補助前は原則0.8%または1.0%) |
| 金利 | 金融機関所定 |
| 保証期間 | 15年以内 |
| 据置期間 | 3年以内 |
| 取扱期間 | 2026年3月31日まで(の保証申込受付分) |
2.信用保証付債権DDSについて
コロナの影響で特に債務超過に苦しむ中小企業者が、既存の保証付融資の一部を資本的劣後債権に転換(DDS)することで、実質債務超過額の圧縮・解消、信用力アップを図り、新たな資金調達を受けやすくするための仕組みです。認定経営革新等支援機関による事業再生計画等が対象となります。
| 信用保証付債権DDSの概要 | |
|---|---|
| 対象者 | 信用保証協会を利用している中小企業者であって、再生計画等を策定し、金融機関等の支援を得て、経営改善・事業再生を図ろうとするもの |
| 劣後化手続き | 信用保証付債権について保証条件変更手続きを行う |
| 期間 | 5年超(事業再生計画等で求められている期間) |
| 償還方法 | 原則として、期限一括返済 |
| 保証料率 | 通常の条件変更手続き同様、貸付実行時の保証料を適用 |
| 金利 | 原則として、配当可能利益に応じた金利設定 |
制度利用の鍵となる「経営行動計画書」と伴走支援の義務
信用保証協会の保証制度などを利用して借換えを行うにあたり、最も重要かつ難易度が高いのが「経営行動計画書」の作成と、それに伴う「伴走支援」の受け入れです。
なぜ計画書が必須なのか?
経営行動計画書は、単に融資を申し込むための形式的な書類ではありません。金融機関や保証協会が借換えを承認し、企業に猶予期間を与えるのは、その企業が猶予期間を「単なる延命」ではなく、「根本的な構造改革」に使うことを確約させるためです。
計画書には、現状の財務状況、資金繰り逼迫の原因分析に始まり、具体的な収益改善策(不採算事業の整理、コスト構造改革、新規販路開拓など)、それらの施策を裏付ける数値目標、そして借換え後の返済シミュレーションを含む財務計画を詳細に盛り込む必要があります。金融機関の融資担当者は、この計画の実効性が高く、企業が回復し、最終的に完済される確信がなければ、支援を承認しません。計画書は、経営者自身の再生への強い意志と、実現可能なロードマップを示すことが必須となります。
伴走支援とは、外部専門家との連携の重要性
伴走支援とは、認定支援機関(税理士、金融機関、コンサルタントなど)が、策定された計画の実行可能性を第三者視点で評価・監督し、計画の進捗に合わせて経営者をサポートすることです。
この外部専門家による支援は、制度上の役割として、計画の客観性と信頼性を高め、金融機関に安心感を与えるための公的なメカニズムとして機能します。実務上のメリットとして、経営者は孤立せず、客観的なデータや専門家の知見を活用しながら迅速に意思決定を行うことが可能となります。特に資金繰りが切迫している状況では、感情的な判断を避け、構造的な問題解決に集中するために、外部専門家の存在は不可欠となります。伴走支援の義務付けは、公的支援が単なる資金提供ではなく、経営改善という成果を求める「条件付き支援」であることを示しています。
借換え申請から実行までの具体的なステップ(実務マニュアル)
既往債務の借換えは、通常の融資手続きよりも複雑であり、既存債務と新規債務の調整が伴うため、緻密な計画と迅速な行動が求められます。
ステップ1:相談と計画策定(早期相談の重要性)
企業再生への第一歩は、早期の専門家相談にあります。資金繰り逼迫が公になり、返済が滞るなど危機が顕在化する前に、専門家(認定支援機関、財務コンサルタントなど)へ相談することが、交渉の余地を確保し、最も有利な制度を選択するための鍵となります。
専門家と共に、事業の現状を詳細に分析し、利用可能な借換え制度(JFC特例、保証協会保証など)を選択します。その後、金融機関が納得する経営行動計画書(または改善計画書)の準備に着手します。この計画策定の段階が、審査の成否を分けます。
ステップ2:仮審査と必要書類の準備
制度を選択し、計画書が大枠で固まったら、金融機関に対して借換えの仮審査を申し込みます。この段階で、申請に必要な多岐にわたる書類の準備がボトルネックとなることが多いです。迅速な申請のためには、書類の入手先とリストを明確にし、漏れなく収集する戦略が必要です。
Table 2: 法人向け 借換え申請時の主な必要書類チェックリスト
| 書類分類 | 具体例 | 主な入手先 | 補足 |
|---|---|---|---|
| 財務状況証明 | 過去3期分の決算報告書 | 会社で保管 | 計画書に基づく改善傾向を強調 |
| 納税状況証明 | 法人税の納税証明書(その1・その2)、所得税の納税証明書(代表者) | 税務署 | 納税状況は企業の信頼性の基礎 |
| 経営計画 | 経営行動計画書(または改善計画書) | 自社作成/専門家と共同作成 | 審査の核となる資料 |
| 代表者関連 | 代表者の源泉徴収票、確定申告書の控え、世帯全員の住民票の写し | 自己で保管/勤め先/市区町村役場 | 法人債務の保証人となる場合などに必要 |
| 契約関連 | 現在の借入契約書、返済予定表、担保物件の登記簿謄本 | 会社で保管/既存金融機関 | 現在の債務状況確認に必要 |
仮審査を通過すると、より詳細な「本審査」に進みます。収入関連書類として、確定申告をしていない給与所得者の代表者の場合は、源泉徴収票や住民税決定通知書、課税証明書などの提出を求められることがあります。
ステップ3:本審査と金融機関との調整
本審査では、提出された経営行動計画書の実行可能性について、金融機関や保証協会との詳細な面談が行われます。この面談では、計画に書かれている内容だけでなく、経営者自身の再生への強い意志、計画に対する理解度、そして計画達成へのコミットメントを明確に伝えることが重要です。
ステップ4:借入中の金融機関への連絡と完済手続き
借換え審査に通過した場合、最も専門的かつミスが許されないのが、新規融資の実行と既存債務の完済手続きです。住宅ローンの借換えと同様に、事業融資の借換えにおいても、以下の事項について、借入中の既存金融機関に連絡し、詳細な調整を行う必要があります4。
このステップは「二重の調整」を意味します。新規融資の実行日と既存債務の完済日を同日に設定し、滞りなく資金を移動させるための緻密な調整が必須となります。確認が必須となる事項は以下の通りです 4。
- 完済受付可能日
- 抵当権抹消書類の受取可能日
- 完済に必要な最終清算額(利息計算を含む)
- 完済金額の振込み先
この最終ステップでの手続き上のミスや連絡の遅延は、借換え自体を無効にするリスクや、既存金融機関との信頼関係を損なう可能性があるため、専門家によるダブルチェックと調整管理が不可欠となります。
利用前に知っておくべきリスクと注意点
既往債務の借換えに活用できる公的な制度は、事業再生の強力なツールですが、その利用には潜在的なコストとリスクが伴います。
金利が上昇する可能性:借換えコストの正確な試算
公的借換え制度の利用によって資金繰りは安定化しますが、金利の面で不利になる可能性があります。コロナ融資など特例的な優遇金利が適用されていた債務を、通常の保証制度や特例制度で借り換える際、全体的な金利水準が高くなる場合があります。
この金利コスト増のリスクを正確に把握するためには、借換え後の総支払額、金利負担額を詳細に試算する必要があります。経営者は、短期的なキャッシュフローの安定化(時間稼ぎ)というメリットが、長期的な金利コスト増というデメリットを上回るか、という経営判断を求められます。事業継続が絶対条件である場合、金利コスト増を許容せざるを得ない場合もありますが、その判断は詳細な試算に基づくべきです。
審査通過のための必須条件:利益改善へのコミットメント
公的な借換え支援制度は、企業の「自助努力による再建」を支援するためのものであり、単に公的資金で債務を肩代わりするためのものではありません。したがって、審査の本質は、提出された経営計画が実現可能であり、企業が確実に回復し、最終的に完済される確信を金融機関に持たせることにあります。
特に信用保証協会系の借換え制度では、伴走支援を受けながら、実現性の高い計画を提出することが審査通過の最低条件となります。計画書が、収益構造の根本的な改善、不採算部門の整理、具体的なコスト削減目標など、痛みを伴う改革を含んでいない場合、審査に通過する可能性は極めて低くなります。審査を受けるということは、経営者が事業再生への強いコミットメントを公的に示す行為となります。
制度を最大限に活用するための専門家への相談
既往債務の借換え支援制度は多岐にわたり、それぞれに複雑なルールが設けられています。また、JFCの特例制度の対象区分や、保証協会制度における伴走支援の要件など、細かな制度設計を把握しなければ、最適な選択を誤る可能性があります。
資金繰りが切迫した状況では、経営者がこれらの複雑な手続きを独力で、迅速かつ正確に進めることは非常に困難です。企業再生の専門家や認定支援機関に早期に相談し、細かなルールを把握することで、事業状況に最も合致し、かつ最も有利な条件を引き出すための道筋を確立することが、成功への近道となります。
まとめと、企業再生へ向けた最初の一歩
既往債務の借換えに活用できる公的な制度は、コロナ融資の返済や物価高騰に直面し、資金繰りに苦しむ中小企業経営者にとって、危機を乗り越え、事業を再スタートさせるための強力な足場となり得ます。この制度は、単なる資金の繰り延べではなく、公的支援をテコとした計画的な構造改革への参加を意味します。特に、経営改善サポート保証(再生支援強化型)のような制度は、優遇された保証料率(0.3%)と、一般保証枠とは別の2億8,000万円という特例的な保証枠を提供することで、事業再生に必要な大きな弾力性をもたらします。
しかし、その支援を受けるためには、経営行動計画書の策定と伴走支援の受け入れという、利益改善への強いコミットメントが求められます。資金繰りの不安を抱えながら独りで悩むのではなく、「早期の相談と計画的な対応」こそが企業再生への第一歩を踏み出す鍵となります。勇気を持って専門家に相談し、公的な支援を最大限に活用して、事業の再建と持続的な発展を目指すことが重要です。
関連記事
-

-
 2025年12月25日(株)WIND-SMILEが民事再生法を申請。負債額は約70億円にのぼる
2025年12月25日(株)WIND-SMILEが民事再生法を申請。負債額は約70億円にのぼる会社名 (株)WIND-SMILE 公式HP https://www.wind-smile.com/...
-
 2025年12月25日中小企業必見!省力化投資補助金(カタログ型)の概要とメリットをわかりやすく解説
2025年12月25日中小企業必見!省力化投資補助金(カタログ型)の概要とメリットをわかりやすく解説人手不足や業務負担の増大に悩む中小企業を支援するために創設されたのが「省力化投資補助金」、正式名称「...
-
 2025年12月25日資金繰り悪化でも再建を諦めないために──事業再生円滑化関連保証の仕組みと活用ポイント
2025年12月25日資金繰り悪化でも再建を諦めないために──事業再生円滑化関連保証の仕組みと活用ポイント資金繰りの悪化や売上減少に直面しながらも、事業の再建を目指す中小企業にとって、再生の初動で資金を確保...
-
 2025年12月25日【2025最新】省力化投資補助金(一般型)の概要と申請要件|カタログ型との違いもわかりやすく整理
2025年12月25日【2025最新】省力化投資補助金(一般型)の概要と申請要件|カタログ型との違いもわかりやすく整理中小企業省力化投資補助金(一般型)は、自社の課題に合わせて柔軟に設備やシステムを選べる点が特徴で、生...